"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。
高層湿原のキセキ [探虫行]
前記事の続きです。(本編は8月27日のことです)
今回の遠征のミッションはふたつ。
ひとつは虫の谷への再トライ、もうひとつはお気に入りの高層湿原を訪れること。
谷に向かう朝、当日の宿泊先はまだ決まっていませんでした。
スワの定宿(民宿)がとれなかったのです。
なので出発前に宿(ゲストハウス)のスタッフにどこかオススメの宿がないか聞いてみたところ・・
あるゲストハウスを教えてくれたのです。
さっそくその場で電話してみると、一部屋だけ空いているとのことで、これ幸いと予約しました。
これで安心して山に向かうことができます。
ミッション1の結果は前記事のとおり。
ミッション2の目的地はこちら。

ここもアキアカネたちが団体さんで下山待ちをしていました。
前日の26日、宿の場所はまったく不案内だったので、所在地をナビに登録してひたすら走りました。
登録地点は国道から脇道を入ってすぐでした。
脇道は細い路地で危うく行き過ぎるところでしたが、すんでのところで左折してナビの地点に到着。
ところが周りを見渡してもゲストハウスらしきものが見当たらない。
もう少し先なのかと思い、徐行しながら少し進みましたが交差点に出てしまいました。
ナビで見るとやはりさっきの場所が正解のようなので引き返す。
さっきの場所まで戻るもやはりそれらしい建物も看板すら見当たらない。
と、左の建物の壁に書いてある店名に何かひっかかるものがありました。
どこかで聞いたか見たかした名前なのだけれど、それはともかく宿が分からないので電話しようと・・
すると、右手から女性が一人歩いて来て、「宿泊のお客さんですか?」
「あ、そうです、今電話しようと思っていたところで・・でも良くわかりましたね」
「バイクでいらっしゃると聞いていたので、バイクの音が聞こえて出てきてみたのです」
よく話を聞くと、一度通り過ぎたバイクの音が戻ってきたようだったからということでした。
それにしても到着時刻を告げていたわけではないのに、気配りのきく宿だなと。
これは裏口の写真ですが、表もこんな看板があるだけで宿の前に車が止まっていると見えないのです。

無事に宿に入って、カウンターで宿帳に名前を書いていたら、住所を見た女性スタッフが。
「わたし○○大学の●●学部出身です」
その学部のキャンパスは地元市内にあり、時々ベニシジミ号で前を通りかかるのでとても身近。
すると、リビングで寛いでいた宿泊者の女性が。
「わたし□□大学の■■学部出身!」
その学部は○○大学のキャンパスの近くで同じ市内。
何でスワまできてこんなローカルな話をすることになるのかと思いつつ、しばしチバ談義。
世の中は斯くも狭きものということですが、不思議なことはこれだけではありませんでした。
さっきのことが気になったのでスタッフの女性に。
「あの向かいのお店はひょっとしてライブハウスですか?」
「そうですよ」
やっぱりかと驚くと同時に鳥肌が立つ思いでした。
何故なら約2週間前、ちょっと訳あってはじめて問い合わせの連絡をしたのがその店だったのです。
場所を知らなかった宿と店。その2軒が路地を挟んで向かい合っていたのです。

スワでのキセキの話はさておき、次の日。
天気予報ではこの日は午前中が勝負のようだったので少し早起きして出発の準備をしていると。
前出のチバからの女性宿泊客が温泉銭湯から帰ってきた。
(近くに温泉銭湯が5軒もあって、どこも5:30から営業している)
どうやら湯治に来ているようで、「マフィンはいかが?」とすすめてくれました。
チバで購入したという、アールグレイマフィンとバナナマフィンは甘くて、おめざに最適でした。

さて、目的地の霧ヶ峰に向けていざ出発。
大平経由で走っていこうとしたのですが、なんと途中でこんな看板が。

したかなくUターンし、R142まで戻って和田峠経由で行くことにしました。
目的地の八島ヶ原に着くと、曇っていたしまだ朝早いこともあり、駐車場は空いていました。
(とはいえ10台以上は止まっていましたが)
さすがに下界とは気温が違うし、雨も想定しなくてはならないので、カッパを装着します。
散策の身支度を整え、湿原の入口に向かおうとしていると、地面に何かが落ちている。

あいにく轢死体でしたが、ここにこの虫がいることがわかった。

さあ、いよいよ久しぶりの高層湿原に突入です。
木道を歩く人影は少ないものの、おそらく植物が狙いのカメラを提げた方が一人先行していました。
朝っぱらからチョウは期待していませんでしたが、この子たちは個体数が多いのでしょう。
先行者に一旦散らされてもまた舞い戻ってきてくれるようでした。

シシウドにいたのは7月に虫の谷で会った子ではないかと。
5~6ミリしかないのですが、このときは風がほとんどなくてなんとか撮影可でした。

曇ってはいたものの薄い陽射しも時折射してくれたので、期待以上に虫影がありました。
ハクサンフウロには朝食中のハナアブが。

この子は敏感なので逃げられないかと緊張しました。
ちなみに湿原内は採集できないので、撮ることに集中です。

そしてこの子を見つけたときはちょっと震えました。

”アオ”ハバチという名ですが、「幸せのグリーンビー」と呼びたい。

少し晩夏の高原の花をフィーチャーします。
これは青。

今年の霧ヶ峰はいつもと違い、この花がまだ見頃でした。

鮮やかな黄色が目立ったのは。

この花の名前は覚えにくい。

ちょうど湿原の反対側で見つけたのは。

これはしばらく後で湿原内に戻ってから撮影したのですが・・

ちょっと色が淡いけど・・タチフウロではないような・・
同系列の色合いのこの花にはあのエトランゼがいてほしい。


湿原を半周したところでシカゲートをくぐり、湿原の外周へ。
人工的な杉の疎林に沿って御射山方面へ。
と、そこへ。
虫の谷では逢えなかったエトランゼが通りがかりました。
優雅に滑空していくのを眺めていると、なぜだか灌木の梢に着地しました。
これはひょっとしてチャンスか?と慌ててリュックから網を出す。(一応持っては来ていた)
ところが長さが足りなくて届かない・・と思ったらふわりと離陸してくれました。
まさかのネットイン。

霧ヶ峰産のアサギマダラが採れてラッキーでした。
この子は生きたまま連れて帰り、昆虫館で生体展示しました。

ゲートをくぐり直して、また湿原内へ。
マツムシソウの群落にヒョウモンちゃんが色を添えてくれていました。
撮れってことでしょう。

このあたりから雨を予感させる風が吹きはじめ、気持ちが急いてくるのを禁じえず。
でも、湿原の辺縁の草原まで戻るとアザミやシシウドなどにヒョウモンちゃんたちが多数出現。
実はその光景を想定していたのでその地点がクライマックスになるよう、左回りに歩いてきたのです。
立ち止まってチョウたちの様子をゆっくり眺めていると、これは予想外のクライマックスが。
どこからか赤と黒の明滅に見えるチョウが飛んできました。
オレンジ色のヒョウモンやエルやシーではなく、ヒオドシとも違うとコンチューターが言ってます。
ここでは採集できないので、観察することに集中していると、草むらの中にとまってくれました。
遠いけど証拠写真を。

このあとすぐ、空が一転俄かに掻き曇ると、みるみるチョウたちは姿を隠しました。
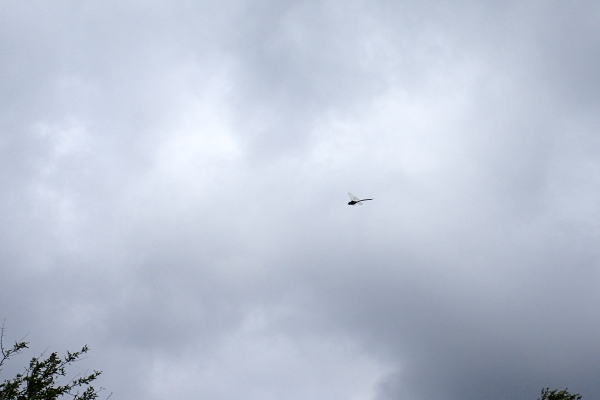
クジャクちゃんもどこかへ消え、戻ってくることはありませんでした。


人の往来も増えはじめたので先を急ごうとしたのですが、通せんぼする子も。

キリギリスは近年分類が見直され、大きくはヒガシキリギリスとニシキリギリスに分かれます。
ヒガシは青森から岡山、ニシは近畿から九州。北海道と沖縄はそれぞれまた別種になります。
最後に少し花を観賞して。

これははじめて見ました。

お見送りをしてくれたのもヒョウモンでした。


来た道で戻るのもつまらないので、とりあえず霧ヶ峰のインターチェンジまで行きました。
雨は思いとどまってくれているようなので、少しパトロールをすることに。
と、その前に。
ちょうど7年前の日に撮影したのと同じ場所(たぶん)で定点撮影。

7年前は快晴で、高原の爽やかさ塗れの一枚でしたが、まあこれはこれで18℃の爽やかさかな。

パトロール先は踊り場湿原。

結局収獲はほぼゼロでしたが、この子たちはちゃんと棲息してくれていることを確認。

この時期はもうボロボロの子しかいません。
あとは虫の谷にもいたバッタ。

それからこの子は幸せのイエローグラスホッパー?


結局、雨に降られることもなく、高原を駆け下りてきました。
そしてスワにもう一泊することにしたのでした。
スワまで降りたところは酒蔵が集まるエリア。いつもの吸蜜場所とも言える。
通り過ぎることができないのはここ。

それとここもお気に入り。

それぞれでお土産を調達して宿へ帰りました。
予定ではこの日チバへ帰るはずだったのに・・
書ききれていないのですが、色々なキセキに満ち溢れた旅でした。
今日の湯加減
今回の遠征のミッションはふたつ。
ひとつは虫の谷への再トライ、もうひとつはお気に入りの高層湿原を訪れること。
谷に向かう朝、当日の宿泊先はまだ決まっていませんでした。
スワの定宿(民宿)がとれなかったのです。
なので出発前に宿(ゲストハウス)のスタッフにどこかオススメの宿がないか聞いてみたところ・・
あるゲストハウスを教えてくれたのです。
さっそくその場で電話してみると、一部屋だけ空いているとのことで、これ幸いと予約しました。
これで安心して山に向かうことができます。
ミッション1の結果は前記事のとおり。
ミッション2の目的地はこちら。

ここもアキアカネたちが団体さんで下山待ちをしていました。
前日の26日、宿の場所はまったく不案内だったので、所在地をナビに登録してひたすら走りました。
登録地点は国道から脇道を入ってすぐでした。
脇道は細い路地で危うく行き過ぎるところでしたが、すんでのところで左折してナビの地点に到着。
ところが周りを見渡してもゲストハウスらしきものが見当たらない。
もう少し先なのかと思い、徐行しながら少し進みましたが交差点に出てしまいました。
ナビで見るとやはりさっきの場所が正解のようなので引き返す。
さっきの場所まで戻るもやはりそれらしい建物も看板すら見当たらない。
と、左の建物の壁に書いてある店名に何かひっかかるものがありました。
どこかで聞いたか見たかした名前なのだけれど、それはともかく宿が分からないので電話しようと・・
すると、右手から女性が一人歩いて来て、「宿泊のお客さんですか?」
「あ、そうです、今電話しようと思っていたところで・・でも良くわかりましたね」
「バイクでいらっしゃると聞いていたので、バイクの音が聞こえて出てきてみたのです」
よく話を聞くと、一度通り過ぎたバイクの音が戻ってきたようだったからということでした。
それにしても到着時刻を告げていたわけではないのに、気配りのきく宿だなと。
これは裏口の写真ですが、表もこんな看板があるだけで宿の前に車が止まっていると見えないのです。

無事に宿に入って、カウンターで宿帳に名前を書いていたら、住所を見た女性スタッフが。
「わたし○○大学の●●学部出身です」
その学部のキャンパスは地元市内にあり、時々ベニシジミ号で前を通りかかるのでとても身近。
すると、リビングで寛いでいた宿泊者の女性が。
「わたし□□大学の■■学部出身!」
その学部は○○大学のキャンパスの近くで同じ市内。
何でスワまできてこんなローカルな話をすることになるのかと思いつつ、しばしチバ談義。
世の中は斯くも狭きものということですが、不思議なことはこれだけではありませんでした。
さっきのことが気になったのでスタッフの女性に。
「あの向かいのお店はひょっとしてライブハウスですか?」
「そうですよ」
やっぱりかと驚くと同時に鳥肌が立つ思いでした。
何故なら約2週間前、ちょっと訳あってはじめて問い合わせの連絡をしたのがその店だったのです。
場所を知らなかった宿と店。その2軒が路地を挟んで向かい合っていたのです。
スワでのキセキの話はさておき、次の日。
天気予報ではこの日は午前中が勝負のようだったので少し早起きして出発の準備をしていると。
前出のチバからの女性宿泊客が温泉銭湯から帰ってきた。
(近くに温泉銭湯が5軒もあって、どこも5:30から営業している)
どうやら湯治に来ているようで、「マフィンはいかが?」とすすめてくれました。
チバで購入したという、アールグレイマフィンとバナナマフィンは甘くて、おめざに最適でした。
さて、目的地の霧ヶ峰に向けていざ出発。
大平経由で走っていこうとしたのですが、なんと途中でこんな看板が。

したかなくUターンし、R142まで戻って和田峠経由で行くことにしました。
目的地の八島ヶ原に着くと、曇っていたしまだ朝早いこともあり、駐車場は空いていました。
(とはいえ10台以上は止まっていましたが)
さすがに下界とは気温が違うし、雨も想定しなくてはならないので、カッパを装着します。
散策の身支度を整え、湿原の入口に向かおうとしていると、地面に何かが落ちている。

オオセンチコガネ (センチコガネ科)
あいにく轢死体でしたが、ここにこの虫がいることがわかった。
さあ、いよいよ久しぶりの高層湿原に突入です。
木道を歩く人影は少ないものの、おそらく植物が狙いのカメラを提げた方が一人先行していました。
朝っぱらからチョウは期待していませんでしたが、この子たちは個体数が多いのでしょう。
先行者に一旦散らされてもまた舞い戻ってきてくれるようでした。

ウラギンヒョウモン (タテハチョウ科)
シシウドにいたのは7月に虫の谷で会った子ではないかと。
5~6ミリしかないのですが、このときは風がほとんどなくてなんとか撮影可でした。

シロホシヒメゾウムシ (ゾウムシ科)
曇ってはいたものの薄い陽射しも時折射してくれたので、期待以上に虫影がありました。
ハクサンフウロには朝食中のハナアブが。

未同定
この子は敏感なので逃げられないかと緊張しました。
ちなみに湿原内は採集できないので、撮ることに集中です。

シラホシカミキリ (カミキリムシ科)
そしてこの子を見つけたときはちょっと震えました。

タカネアオハバチ (ハバチ科)
”アオ”ハバチという名ですが、「幸せのグリーンビー」と呼びたい。
少し晩夏の高原の花をフィーチャーします。
これは青。

ヒメトラノオ
今年の霧ヶ峰はいつもと違い、この花がまだ見頃でした。

ヤナギランとアキアカネ
鮮やかな黄色が目立ったのは。

オミナエシとハナアブ
この花の名前は覚えにくい。

オオヒナノウスツボ
ちょうど湿原の反対側で見つけたのは。

アサマフウロ
これはしばらく後で湿原内に戻ってから撮影したのですが・・

同上
ちょっと色が淡いけど・・タチフウロではないような・・
同系列の色合いのこの花にはあのエトランゼがいてほしい。

シモツケソウ
湿原を半周したところでシカゲートをくぐり、湿原の外周へ。
人工的な杉の疎林に沿って御射山方面へ。
と、そこへ。
虫の谷では逢えなかったエトランゼが通りがかりました。
優雅に滑空していくのを眺めていると、なぜだか灌木の梢に着地しました。
これはひょっとしてチャンスか?と慌ててリュックから網を出す。(一応持っては来ていた)
ところが長さが足りなくて届かない・・と思ったらふわりと離陸してくれました。
まさかのネットイン。

アサギマダラ (タテハチョウ科)
霧ヶ峰産のアサギマダラが採れてラッキーでした。
この子は生きたまま連れて帰り、昆虫館で生体展示しました。
ゲートをくぐり直して、また湿原内へ。
マツムシソウの群落にヒョウモンちゃんが色を添えてくれていました。
撮れってことでしょう。

マツムシソウとウラギンヒョウモン
このあたりから雨を予感させる風が吹きはじめ、気持ちが急いてくるのを禁じえず。
でも、湿原の辺縁の草原まで戻るとアザミやシシウドなどにヒョウモンちゃんたちが多数出現。
実はその光景を想定していたのでその地点がクライマックスになるよう、左回りに歩いてきたのです。
立ち止まってチョウたちの様子をゆっくり眺めていると、これは予想外のクライマックスが。
どこからか赤と黒の明滅に見えるチョウが飛んできました。
オレンジ色のヒョウモンやエルやシーではなく、ヒオドシとも違うとコンチューターが言ってます。
ここでは採集できないので、観察することに集中していると、草むらの中にとまってくれました。
遠いけど証拠写真を。

クジャクチョウ (タテハチョウ科)
このあとすぐ、空が一転俄かに掻き曇ると、みるみるチョウたちは姿を隠しました。
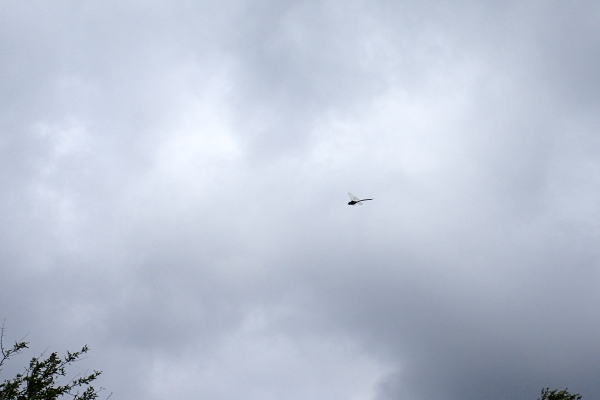
クジャクちゃんもどこかへ消え、戻ってくることはありませんでした。

人の往来も増えはじめたので先を急ごうとしたのですが、通せんぼする子も。

キリギリス (キリギリス科)
キリギリスは近年分類が見直され、大きくはヒガシキリギリスとニシキリギリスに分かれます。
ヒガシは青森から岡山、ニシは近畿から九州。北海道と沖縄はそれぞれまた別種になります。
最後に少し花を観賞して。

ヤマトリカブト
これははじめて見ました。

イワアカバナ
お見送りをしてくれたのもヒョウモンでした。

ウラギンヒョウモン ♀ (タテハチョウ科)
来た道で戻るのもつまらないので、とりあえず霧ヶ峰のインターチェンジまで行きました。
雨は思いとどまってくれているようなので、少しパトロールをすることに。
と、その前に。
ちょうど7年前の日に撮影したのと同じ場所(たぶん)で定点撮影。

7年前は快晴で、高原の爽やかさ塗れの一枚でしたが、まあこれはこれで18℃の爽やかさかな。
パトロール先は踊り場湿原。

結局収獲はほぼゼロでしたが、この子たちはちゃんと棲息してくれていることを確認。

ヒメシジミ (シジミチョウ科)
この時期はもうボロボロの子しかいません。
あとは虫の谷にもいたバッタ。

ミヤマヒナバッタ (バッタ科)
それからこの子は幸せのイエローグラスホッパー?

ナキイナゴ ♂(バッタ科)
結局、雨に降られることもなく、高原を駆け下りてきました。
そしてスワにもう一泊することにしたのでした。
オマケ
スワまで降りたところは酒蔵が集まるエリア。いつもの吸蜜場所とも言える。
通り過ぎることができないのはここ。

宮坂醸造
それとここもお気に入り。

舞姫酒造
それぞれでお土産を調達して宿へ帰りました。
予定ではこの日チバへ帰るはずだったのに・・
書ききれていないのですが、色々なキセキに満ち溢れた旅でした。
今日の湯加減
少し久しぶりに訪れることができた高原でしたが、チバに帰ると猛暑に逆戻り。
と思ったら、9月になった途端、空気が変わりました。
あんなに大発生して夜中まで鳴いていたアブラゼミの声がしなくなり、ソロはツクツクボウシに。
代わりにコオロギ、アオマツムシ、カネタタキなどのバッタたちの合唱がはじまりました。
台風も来ているし、残暑が戻ってくるかもしれませんが、遥かなる高原はすっかりもう秋でしょう。
"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。





オオウラギンのお見送りとはまた、ぜいたくな。最近数を減らしているとの情報もありますが・・・
お初にコメントさせていただきます。愛読させていただいております。よろしくお願いいたします。
ところで、クジャクさんの写真のバックはワレモコウですか?
by たかわ (2019-09-07 19:31)
タカネアオハバチ、ブルーの目が印象的な可愛らしい虫でやすね。
珍しいのでやすね!
by ぼんぼちぼちぼち (2019-09-08 17:41)
>たかわさん
ご愛読ありがとうございます。
お見送りはオオウラギンではなく、ウラギンのメスでした。
勇み足をしてしまいすみません。訂正しました。
>ぼんぼちぼちぼちさん
幸せ色のハバチに会えて運気が上昇したと思います!^^
青い目も魅惑的ですね♪
by ぜふ (2019-09-08 20:34)
報告です!
八王子出身の野生児ブンタ3世とフーコ2世、卵がっつり産んでいて、すでに孵化しました^^;
いきなり幼虫20匹で、びっくりびっくり!
by リュカ (2019-09-08 23:56)
コメント入るかな…
おととい庭にクジャクチョウが遊びに来てくれてびっくり!
やはり山の家は立派な山の中みたい(笑)
今朝も大きなトンボが飛んでます。
黒地に青のシマシマの綺麗なトンボ^^
by よしころん (2019-09-09 13:14)
>リュカさん
よかったですね♪
来年に向けて大事に育ててください。
>よしころんさん
クジャクチョウが訪れる庭があると何かがマヒしそうでこわい。
ルリボシヤンマですかね・・もう完全マヒ^^
by ぜふ (2019-09-09 22:45)
こんばんは!
ツーリングと虫探訪、何とも羨ましいです。
霧ヶ峰や和田峠も長らくご無沙汰ですが、もう体力的にバイクは無理かもしれません。
でもいつか幸せのグリーンビーを見てみたいです!!
by hirokou (2019-09-12 20:04)
「ハバチ」は「蜂」でしょうか。ハチのようには見えませんが...。
私もこのタカネアオハバチ、小さいながらも青い目のインパクトが
強烈です^^;。
旅先でのこういう偶然も、楽しいですよねぇ。
by sakamono (2019-09-12 22:12)
>hirokouさん
ベニシジミ号は軽快ですから、まだまだいけますよ!^^
グリーンビーはもう少しゆっくり観察したかった・・
ぜひ、幸せのグリーンビーに会いにでかけてください!
>sakamonoさん
蜂です。ハバチはミツバチの仲間とは生態もかなり違いますね。
偶然の出会いも旅の醍醐味ですね♪
ニンゲンとも^^
by ぜふ (2019-09-12 23:16)
こんにちは^^
いろいろキセキは起こるものですね~
タカネアオハバチって目のグリーンが綺麗~♪
ブルービーはブログで見たことがありますが、
これもあのような蜂なんですか?
お花も虫も沢山居ましたね。
by mimimomo (2019-09-13 11:55)
>mimimomoさん
ブルービーはミツバチ科なので違う科ですね。
旅はキセキが起きやすいですが、今回は特別でした^^
by ぜふ (2019-09-13 22:03)