"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。
髭長花蚤 [観察会]
月2回のHF観察会。遠出ができないときの目的地の第一候補。
と言いながら、5月19日は遠出ができたのですが、疲れがたまっていたので無理しないことにして・・
午前中は観察会に出て、午後は溜まりに溜まった所用をこなすことにしました。
本格的にシーズンインして、記事化が間に合わない状態なのでその2回分をまとめます。
メインキャストはこの子にしますが、誰だかわかりますか?

当むしブロには何度も登場していますので見覚えがあるのではと。
答えの前に。
この日のテーマのひとつはトンボだったので、参加者は一生懸命網を振っていました。
手乗りにさせた子もいました。

見慣れないトンボが梢にとまったのを見つけました。
でも遠すぎて写真は撮れません。観察指導員の方に網を借りて採ってみると・・

キイロサナエとよく似ていますが、胸側面の下から2本目の黒い筋が繋がっているかどうかで判定可。
HFでははじめて観察しました。他にも採った子がいたので複数頭いたようです。
小さな水路沿いにはHFのレギュラーメンバーのカワトンボがいました。

メスもいましたが撮らせてくれず。
ちょっとだけ粘りましたが、今年はまだ個体数が少ないようで結局撮れませんでした。
その代わりというには全く脈略がないですが・・

まさに若葉色ですが、葉っぱを食べているわけではないのに、どうしてこれほど同じ色になるのかな。

さて、扉の写真の答えです。
正解はというか、全身写真はこちら。

過去に同じことを書いたかもしれませんが、この虫の名前はちょっと面白い。
ヒゲナガハナノミ・・・どこで切るのでしょう。
見た目の印象もあって、どうしても、ヒゲナガ・ハナノミ と区切りたくなります。
でも、ハナノミ科ではなく、ナガハナノミ科なのです。
つまり、ヒゲ・ナガハナノミ なのです。
漢字で書くと 髭長花蚤。
マルハナノミ科と比べて体が長細いのがナガハナノミ科。
トビハムシのようにぴょんぴょん飛ぶわけではないのに、どうして花蚤というかは分かりません。
とにかく、オスは櫛状の長い髭が特徴なので、ヒゲナガ・ナガハナノミ を約めたのかも。
メスはこちら。

ヒゲナガハナノミは今年とても多く発生していました。
こちらは6月2日に撮影したオスメス。


カワトンボのメスを探して少し谷津田の奥に行こうとしたとき、足元にこの子がいました。

HFでは久しぶりのご対面。

何の糞に依存しているのでしょう・・

ここからは6月2日。田んぼの縁の葉の上にいた、ちびっ子ライダーたち。
これはたぶんオンブバッタの幼虫。

これはたぶんツチイナゴの幼虫。

ちなみに成虫はこんな感じ。


いつものように、観察会が終わってもこうして畦にうんこ座りして撮影していたのですが。
片付けをしていたスタッフの方に「ぜふさ~ん!」と呼ばれました。
「どうしましたか~」
「蛾がいました~」
翻訳すると、種類が分からないから同定しろ ということですが・・
「蛾はわからないんですよね~」
と言いながらやっぱり気になるので行ってみると、地面をちょこまかと歩いている大きな蛾が。

なかなか歩くのが早くて、どうしてもブレてしまいます。
スタッフの一人が「とまれ~!」と叫びましたが、当然とまることはなく。
別のスタッフが枝を差し出すと、それにつかまって落ち着いてくれました。

この子はまったくの初見で、家に帰ってから図鑑で同定しましたが、モヒカン頭が特徴。
それとこれでもかというほど、もふもふの脚も特徴的ですね。
ということで、お初の虫にいくつか会えて満足したHF観察会でした。
HFではお初の子をもう一種。
なんとか生態写真を撮りたかったのですが、最初に見つけた個体はとにかく走り回って撮れず。
半ヤラセで平らな畦道において、走り回るのをしばらく追いかけてみましたが、全く停止してくれず。
ところが、帰り道ふと湧水のところに寄ってみたら、木道の隙間に。

逃げ出す前にシャッターを切らねばと焦ってしまったのと、隙間だったのでアングルがとれませんでした。
でもまあ、一応生態写真が撮れて満足。
ところで。
前記事で紹介したクワコの幼虫「こまったちゃん」
お連れした翌日に繭になりました。

それから約2週間後の昨日、こまったちゃんの繭を入れた飼育ケースの中からブンブンという音が・・
残念ながら寄生されていたようです。
こんな子たちが何匹も・・

これもカイコとは違い、野生種の宿命のうちです。
今日の湯加減
と言いながら、5月19日は遠出ができたのですが、疲れがたまっていたので無理しないことにして・・
午前中は観察会に出て、午後は溜まりに溜まった所用をこなすことにしました。
本格的にシーズンインして、記事化が間に合わない状態なのでその2回分をまとめます。
メインキャストはこの子にしますが、誰だかわかりますか?

当むしブロには何度も登場していますので見覚えがあるのではと。
答えの前に。
この日のテーマのひとつはトンボだったので、参加者は一生懸命網を振っていました。
手乗りにさせた子もいました。

シオヤトンボ ♂(トンボ科)
見慣れないトンボが梢にとまったのを見つけました。
でも遠すぎて写真は撮れません。観察指導員の方に網を借りて採ってみると・・

ヤマサナエ ♀(サナエトンボ科)
キイロサナエとよく似ていますが、胸側面の下から2本目の黒い筋が繋がっているかどうかで判定可。
HFでははじめて観察しました。他にも採った子がいたので複数頭いたようです。
小さな水路沿いにはHFのレギュラーメンバーのカワトンボがいました。

ニホンカワトンボ ♂ (カワトンボ科)
メスもいましたが撮らせてくれず。
ちょっとだけ粘りましたが、今年はまだ個体数が少ないようで結局撮れませんでした。
その代わりというには全く脈略がないですが・・

ワカバグモ
まさに若葉色ですが、葉っぱを食べているわけではないのに、どうしてこれほど同じ色になるのかな。
さて、扉の写真の答えです。
正解はというか、全身写真はこちら。

ヒゲナガハナノミ ♂ (ナガハナノミ科)
過去に同じことを書いたかもしれませんが、この虫の名前はちょっと面白い。
ヒゲナガハナノミ・・・どこで切るのでしょう。
見た目の印象もあって、どうしても、ヒゲナガ・ハナノミ と区切りたくなります。
でも、ハナノミ科ではなく、ナガハナノミ科なのです。
つまり、ヒゲ・ナガハナノミ なのです。
漢字で書くと 髭長花蚤。
マルハナノミ科と比べて体が長細いのがナガハナノミ科。
トビハムシのようにぴょんぴょん飛ぶわけではないのに、どうして花蚤というかは分かりません。
とにかく、オスは櫛状の長い髭が特徴なので、ヒゲナガ・ナガハナノミ を約めたのかも。
メスはこちら。

同上 ♀
ヒゲナガハナノミは今年とても多く発生していました。
こちらは6月2日に撮影したオスメス。

同上 ♂

同上 ♀
カワトンボのメスを探して少し谷津田の奥に行こうとしたとき、足元にこの子がいました。

HFでは久しぶりのご対面。

センチコガネ (センチコガネ科)
何の糞に依存しているのでしょう・・
ここからは6月2日。田んぼの縁の葉の上にいた、ちびっ子ライダーたち。
これはたぶんオンブバッタの幼虫。

これはたぶんツチイナゴの幼虫。

ちなみに成虫はこんな感じ。

ツチイナゴ (バッタ科)
いつものように、観察会が終わってもこうして畦にうんこ座りして撮影していたのですが。
片付けをしていたスタッフの方に「ぜふさ~ん!」と呼ばれました。
「どうしましたか~」
「蛾がいました~」
翻訳すると、種類が分からないから同定しろ ということですが・・
「蛾はわからないんですよね~」
と言いながらやっぱり気になるので行ってみると、地面をちょこまかと歩いている大きな蛾が。

なかなか歩くのが早くて、どうしてもブレてしまいます。
スタッフの一人が「とまれ~!」と叫びましたが、当然とまることはなく。
別のスタッフが枝を差し出すと、それにつかまって落ち着いてくれました。

セダカシャチホコ ♂ (シャチホコガ科)
この子はまったくの初見で、家に帰ってから図鑑で同定しましたが、モヒカン頭が特徴。
それとこれでもかというほど、もふもふの脚も特徴的ですね。
ということで、お初の虫にいくつか会えて満足したHF観察会でした。
オマケ
HFではお初の子をもう一種。
なんとか生態写真を撮りたかったのですが、最初に見つけた個体はとにかく走り回って撮れず。
半ヤラセで平らな畦道において、走り回るのをしばらく追いかけてみましたが、全く停止してくれず。
ところが、帰り道ふと湧水のところに寄ってみたら、木道の隙間に。

コキベリアオゴミムシ (オサムシ科)
逃げ出す前にシャッターを切らねばと焦ってしまったのと、隙間だったのでアングルがとれませんでした。
でもまあ、一応生態写真が撮れて満足。
ところで。
前記事で紹介したクワコの幼虫「こまったちゃん」
お連れした翌日に繭になりました。

それから約2週間後の昨日、こまったちゃんの繭を入れた飼育ケースの中からブンブンという音が・・
残念ながら寄生されていたようです。
こんな子たちが何匹も・・

これもカイコとは違い、野生種の宿命のうちです。
今日の湯加減
今日は奥本先生とある出版社のレジェンド編集者N氏との対談に同席させてもらいました。
著書発刊、重版、書店との駆け引きなどの裏話も聞けました。(もちろんここでは書けません)
それと、今週は仕事にかまけて某県某所へ探虫に行ってもきました。
どちらも貴重な時間を過ごせ、充実した日々を過ごしていますが、時間が足りない。
でも、そんなにやる事が膨大にあるわけではないんだなぁ。
もっとテキカクに頭を回転させ、もっとテキパキと体を動かせれば、時間は足りるのじゃないかと。
かと言って、自分を叱咤して必死になるほど切羽詰まっているわけでもない。
或いはまた、崖っぷち気分を楽しめる余裕があるわけでもない。
ファーブル昆虫館監修「昆虫知育ぶっく」発刊されました!
"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。
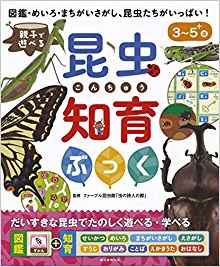





ナガハナノミは蛍のように光りそうですね。
トンボを手に留まらせるとは
どんな技?
by 響 (2019-06-11 12:32)
こまったちゃん、残念でしたね…
繭はとても綺麗なのに。
by よしころん (2019-06-12 16:12)
ヒゲナガハナノミ。
漢字で書いたのを見ると、なるほどと納得です。
我が家のカブトムシ、フーコちゃんはすこぶる元気で、卵を一個だけ確認しました。
ブンタ2世はフーコよりは物静かなかんじです。
by リュカ (2019-06-13 15:50)
やっぱトンボは美しいでやすね。
特に羽の赤いのが綺麗だなあと思いやした。
by ぼんぼちぼちぼち (2019-06-13 20:49)
>響さん
ホタルの仲間ではないので残念ながら光らないですが同じ形ですね^^
手乗りトンボは子供ならではの技?いや少年の心があれば誰でも♪
>よしころんさん
自然はきびしいですね。
しかもサナギになるのを待って脱出するわけで・・
美しい繭の糸が哀愁をさそいます。
>リュカさん
漢字がわかりやすいですね^^
オスはしずかで、メスはにぎやか・・ニンゲンと同じ?^^
卵産んでよかった。
>ぼんぼちぼちぼちさん
ボツにしようかと思った写真でしたが救われました^^
赤い翅はオスです♪
by ぜふ (2019-06-13 21:55)
ヒゲナガ・ハナノミと読みました^^;。
クワコは、繭もワイルドな感じがしますねぇ。
寄生している虫は、宿主が繭になると活動を
開始するような感じなのでしょうか。
自然の驚異を感じます。
by sakamono (2019-06-13 22:03)
>sakamonoさん
マルハナノミの存在を知っていれば間違わないんでしょうね。
クワコの蚕糸の色は美しいですが、自然はきびしいですね。
by ぜふ (2019-06-15 09:00)