"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。
掘りすぎ注意 [オサムシ]
11月3日、前々日時点のチバの天気予報は、午前中の降水確率70%、午後は30%で雨のち曇り。
実は外房か南房かどっちか迷っていたのですが、めずらしく外房の九十九里も南房総の館山も同じ予報。
ならば遠い方がいい。 移動しているうちに天気が好転していくから。
ということで、ファーブル会オサ部の若きエースのK君を連れて、館山へ試掘に行ってきました。

朝、K君をピックアップした時点では曇天でしたが、目論見どおりだんだん晴れてきて、木更津を過ぎたあたりでは晴天に。
はじめて訪れるフィールドでしたが、ここもGoogle Mapで貯水池(調整池)を探し、その周辺の森や林や林道の様子をGoogle Earthで確認して決定するという、もはやお決まりの探し方で候補地としたのでした。
ところが、現地に着いてみたら、水がありませんでした。

ほぼ干上がって池底は原っぱと化していたので調整池ではないということでしょうか。
池の縁が小崖となっていることと何本か立ち枯れの木があるのに二人ともすぐ気が付きました。
ならば、ますば下に降りてみようということに。

池底の原っぱにはオンブバッタとこのバッタがたくさんいました。

翅が長いヒシバッタで、田んぼや湿地に生息しています。まさにここは適地でしょう。

さて、”試掘”の対象はもちろんオサムシ。
今回はオサムシの仲間であるゴミムシ類をターゲットにしたポイント探しの旅でした。
今年の秋は短く、もう晩秋といってもいい気候なので、そろそろ試掘の時期ということです。
しかるに二人は、意気揚々と池の縁にそれぞれ取り縋り、土を掘り返していきました。
ところが、掘れども掘れども何も出てきません。
ゴミムシ一匹すら。
ミミズやムカデなどの指標生物もでないので、ここにはいないと判断しました。
つまり、この池は干上がってそれほど時間は経っていないということです。
やはり調整池なのでしょう。これからまた水が溜められることもあるのだと思います。
それを虫たちは知っているのです。 水没リスクがある場所で冬眠するほど彼らはマヌケではない。
と、「こんなの出ました~」とK君の声。
そんな判断は浅はかだったのかと一瞬戸惑いましたが、行ってみると出たのは・・

K君も崖は見切って、池の縁から倒れた朽木に目をつけていたのです。
やはりワイルド(天然もの)は立派なサイズ。

もう崖を掘るのはやめて、立ち枯れの木も攻めてみましたが空振り。
池の中はあきらめて地上に戻りました。

道路から林の中へ向かう獣道に入ってみました。

そこにも小崖があったので掘っていると、すぐさまエースが掘り当てました。

でも後が続きませんでした。
これから越冬するトンボには会えました。

扉の写真のオオアオイトトンボと同じ、アオイトトンボの仲間ですが、越冬するのでこういう保護色なのです。
2匹目のゴミムシは出ず、獣道はすぐ藪の中になったので、このポイントの試掘は終了としました。

近くの別の貯水池へ移動しました。 (こちらはホントの池)
池の周囲は目ぼしいポイントがなさそうだったのですが、池の下流の田んぼの周辺を探索することに。
田んぼ脇の細い農道を挟んだ林縁が崖になっている個所がありました。
ただ、ほぼ岩盤でなかなか掘れない。
でもK君は2匹目を出しました。

他にミイデラゴミムシも出ましたがそれだけでした。
こちらはまたもや何も出せず。
木の葉の上にこの子を見つけただけ。

サトクダマキモドキかと思っていましたが、帰ってから調べてみるとレアな”ヒメ”の方でした。

三芳村の道の駅でお昼を食べながら作戦会議をしました。
悩んだ末、せっかく館山まで来たのだから未踏の地で様子を知りたかった富山(とみさん)へ向かうことに。
三芳村からは車で15分ほど。 ナビで麓までは行けたのですが、登り口がわかりません。
それらしい道の入り口に車を止めて降りると、ちょうど目の前のお宅から人が出てきたので尋ねてみました。
すると、この道ではなく、少し戻った自動販売機があるところから車で途中まで登っていけるとのこと。
そこから登っていくと山の斜面にはみかん畑がひろがり、南房総の温かさを実感しました。

この子も元々は南方系の蝶で徐々に北上東進しているのですが、温かい南房総はまさに適地でしょうね。
車で行けるところまで登り、そこから徒歩で急こう配の道を頂上目指して歩きましたが適当なポイントなし。
様子はわかったので早々に見切りをつけて、こちらも北上して別の山へ向かいました。

向かったのは鋸山。
「房総のトンボ池」の記事でも紹介したフィールド、そこはオサムシがいるはずでポイントもわかっている。

鋸山自体は岩山なので固くて掘れない崖地ばかりですが、あるエリアの山道沿いは粘土質の小崖があるのです。
それほど大きくはないですが、まさに理想的なオサ掘りフィールドなので、何某かは出ると思っていました。
ところが。
二人で掘っても掘っても、崩しても崩しても何も出ない。
ここはとっておきのポイントだったのに。
唯一、K君が掘り出したのは。

集団越冬しているハンミョウです。
かわいそうだけど掘り出してみると、4匹が固まっていました。
(お連れしてファーブル館で生体展示しています)

もうかなり陽が傾いてきていて、おそらく残り時間は1時間もない。
ならばこのままここで粘るより、もう一度移動してラスト30分にかけようと決めました。
15分ほどで最後のポイントに到着。
小崖は少ないのですが、夏はゴミムシなどの虫影が濃いエリアなのです。
でも、時間がないので手あたり次第に掘ることはできません。
ここぞという所を見定めて、バチツルを振り下ろします。
そしてついに出ました。

しかも。

このブログでは何度も紹介している、アオオサムシの房総亜種です。
”アオ”オサムシなのに、まったく青くないのです。
これを見てK君も奮い立ったようで、ずんずん山道を登りながら掘っていきました。
そして彼もゴミムシ発掘。


アカオサが出なければ、一日を通してもボウズになるところでした。
総括すると、今年の秋は短く、朝晩は冷え込み、もうすでに晩秋と言っていいはず。
しかしこれほどまでに出なかったということは、潜っている個体数がまだ少なかったのではないかと。
その仮説を検証するために、今シーズン中にまた時期を変えて、同じポイントで探虫してみようと思います。
「そう考えるとあまり掘らない方がよかったね」
とK君に言うと。
「でもリベンジはしたいですね!」
9月のはじめにスキー場を巡ってオサムシ探しをしたとき。
あるスキー場で偶然見つけた虫。

日本にエンマムシは100種類もいるそうで、同定ができていませんでしたが、昆虫館の図鑑で調べました。
前胸の縁の条紋が2本あることで、ヤマトエンマムシと判断。
今、目の前でミールワームを食べています。
今日の湯加減
実は外房か南房かどっちか迷っていたのですが、めずらしく外房の九十九里も南房総の館山も同じ予報。
ならば遠い方がいい。 移動しているうちに天気が好転していくから。
ということで、ファーブル会オサ部の若きエースのK君を連れて、館山へ試掘に行ってきました。

館山市某所
朝、K君をピックアップした時点では曇天でしたが、目論見どおりだんだん晴れてきて、木更津を過ぎたあたりでは晴天に。
はじめて訪れるフィールドでしたが、ここもGoogle Mapで貯水池(調整池)を探し、その周辺の森や林や林道の様子をGoogle Earthで確認して決定するという、もはやお決まりの探し方で候補地としたのでした。
ところが、現地に着いてみたら、水がありませんでした。

ほぼ干上がって池底は原っぱと化していたので調整池ではないということでしょうか。
池の縁が小崖となっていることと何本か立ち枯れの木があるのに二人ともすぐ気が付きました。
ならば、ますば下に降りてみようということに。

池底の原っぱにはオンブバッタとこのバッタがたくさんいました。

トゲヒシバッタ (ヒシバッタ科)
翅が長いヒシバッタで、田んぼや湿地に生息しています。まさにここは適地でしょう。
さて、”試掘”の対象はもちろんオサムシ。
今回はオサムシの仲間であるゴミムシ類をターゲットにしたポイント探しの旅でした。
今年の秋は短く、もう晩秋といってもいい気候なので、そろそろ試掘の時期ということです。
しかるに二人は、意気揚々と池の縁にそれぞれ取り縋り、土を掘り返していきました。
ところが、掘れども掘れども何も出てきません。
ゴミムシ一匹すら。
ミミズやムカデなどの指標生物もでないので、ここにはいないと判断しました。
つまり、この池は干上がってそれほど時間は経っていないということです。
やはり調整池なのでしょう。これからまた水が溜められることもあるのだと思います。
それを虫たちは知っているのです。 水没リスクがある場所で冬眠するほど彼らはマヌケではない。
と、「こんなの出ました~」とK君の声。
そんな判断は浅はかだったのかと一瞬戸惑いましたが、行ってみると出たのは・・

K君も崖は見切って、池の縁から倒れた朽木に目をつけていたのです。
やはりワイルド(天然もの)は立派なサイズ。

カブトムシの幼虫 (コガネムシ科)
もう崖を掘るのはやめて、立ち枯れの木も攻めてみましたが空振り。
池の中はあきらめて地上に戻りました。

(種名不明)
道路から林の中へ向かう獣道に入ってみました。

ツチイナゴ (バッタ科)
そこにも小崖があったので掘っていると、すぐさまエースが掘り当てました。

オオゴミムシ (オサムシ科)
でも後が続きませんでした。
これから越冬するトンボには会えました。

ホソミオツネントンボ (アオイトトンボ科)
扉の写真のオオアオイトトンボと同じ、アオイトトンボの仲間ですが、越冬するのでこういう保護色なのです。
2匹目のゴミムシは出ず、獣道はすぐ藪の中になったので、このポイントの試掘は終了としました。
近くの別の貯水池へ移動しました。 (こちらはホントの池)
池の周囲は目ぼしいポイントがなさそうだったのですが、池の下流の田んぼの周辺を探索することに。
田んぼ脇の細い農道を挟んだ林縁が崖になっている個所がありました。
ただ、ほぼ岩盤でなかなか掘れない。
でもK君は2匹目を出しました。

オオゴミムシ (オサムシ科)
他にミイデラゴミムシも出ましたがそれだけでした。
こちらはまたもや何も出せず。
木の葉の上にこの子を見つけただけ。

ヒメクダマキモドキ (ツユムシ科)
サトクダマキモドキかと思っていましたが、帰ってから調べてみるとレアな”ヒメ”の方でした。
三芳村の道の駅でお昼を食べながら作戦会議をしました。
悩んだ末、せっかく館山まで来たのだから未踏の地で様子を知りたかった富山(とみさん)へ向かうことに。
三芳村からは車で15分ほど。 ナビで麓までは行けたのですが、登り口がわかりません。
それらしい道の入り口に車を止めて降りると、ちょうど目の前のお宅から人が出てきたので尋ねてみました。
すると、この道ではなく、少し戻った自動販売機があるところから車で途中まで登っていけるとのこと。
そこから登っていくと山の斜面にはみかん畑がひろがり、南房総の温かさを実感しました。

ムラサキツバメ (シジミチョウ科)
この子も元々は南方系の蝶で徐々に北上東進しているのですが、温かい南房総はまさに適地でしょうね。
車で行けるところまで登り、そこから徒歩で急こう配の道を頂上目指して歩きましたが適当なポイントなし。
様子はわかったので早々に見切りをつけて、こちらも北上して別の山へ向かいました。
向かったのは鋸山。
「房総のトンボ池」の記事でも紹介したフィールド、そこはオサムシがいるはずでポイントもわかっている。

鋸山自体は岩山なので固くて掘れない崖地ばかりですが、あるエリアの山道沿いは粘土質の小崖があるのです。
それほど大きくはないですが、まさに理想的なオサ掘りフィールドなので、何某かは出ると思っていました。
ところが。
二人で掘っても掘っても、崩しても崩しても何も出ない。
ここはとっておきのポイントだったのに。
唯一、K君が掘り出したのは。

ハンミョウ (オサムシ科)
集団越冬しているハンミョウです。
かわいそうだけど掘り出してみると、4匹が固まっていました。
(お連れしてファーブル館で生体展示しています)
もうかなり陽が傾いてきていて、おそらく残り時間は1時間もない。
ならばこのままここで粘るより、もう一度移動してラスト30分にかけようと決めました。
15分ほどで最後のポイントに到着。
小崖は少ないのですが、夏はゴミムシなどの虫影が濃いエリアなのです。
でも、時間がないので手あたり次第に掘ることはできません。
ここぞという所を見定めて、バチツルを振り下ろします。
そしてついに出ました。

しかも。

アカオサムシ (オサムシ科)
このブログでは何度も紹介している、アオオサムシの房総亜種です。
”アオ”オサムシなのに、まったく青くないのです。
これを見てK君も奮い立ったようで、ずんずん山道を登りながら掘っていきました。
そして彼もゴミムシ発掘。

スジアオゴミムシ (オサムシ科)
アカオサが出なければ、一日を通してもボウズになるところでした。
総括すると、今年の秋は短く、朝晩は冷え込み、もうすでに晩秋と言っていいはず。
しかしこれほどまでに出なかったということは、潜っている個体数がまだ少なかったのではないかと。
その仮説を検証するために、今シーズン中にまた時期を変えて、同じポイントで探虫してみようと思います。
「そう考えるとあまり掘らない方がよかったね」
とK君に言うと。
「でもリベンジはしたいですね!」
オマケ
9月のはじめにスキー場を巡ってオサムシ探しをしたとき。
あるスキー場で偶然見つけた虫。

ヤマトエンマムシ (エンマムシ科)
日本にエンマムシは100種類もいるそうで、同定ができていませんでしたが、昆虫館の図鑑で調べました。
前胸の縁の条紋が2本あることで、ヤマトエンマムシと判断。
今、目の前でミールワームを食べています。
今日の湯加減
オサ屋にシーズンオフはないと前回書きましたが、冬も探虫するからです。
というわけでTG-4もまだ修理に出せていません。
色々あって最近、湯加減が低下中です。(ドナルドさんのことは関係ありません)
パソコンもまだ復旧できていません。
この記事も昨日アップする予定でしたが、どうも筆が・・いや、キーボードが進まず。
今日はこれからお江戸の若者の街にでかけて、古い知り合いのライブを見てきます。
ローテンションでは見れないと思うのですが、ハイテンションにはなれそうにない気がします。
が、気分転換にはなると思うので、楽しんできます!
「おれ今日バイク」 最高です!
"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。
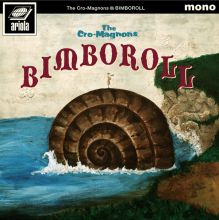





こんばんは^^
良かったですね~坊主じゃなくって^^
確かに秋が短かったですよね。
by mimimomo (2016-11-13 20:40)
房総にはまだトンボもいるのですね~
山はだんだんと寂しくなってきました・・・^^;
by よしころん (2016-11-13 22:34)
最近山では昆虫を余り見なくなりました。越冬し始めたんですかね。当地では郊外で熊の被害が続出してます、そちらでは・・・
by g_g (2016-11-14 08:13)
若きエースさん
なかなかのセンスをお持ちですね。
宝石を掘ってるみたいで楽しそう。
by 響 (2016-11-14 12:12)
>mimimomoさん
ほとんにこの一匹だけでした^^;
近年の季節は気まぐれ。 また秋が来るかもしれませんね^^;
>よしころんさん
オオアオイトトンボは11月までいますね~
オツネントンボは越冬しますからまだまだ観察機会があります♪
>g_gさん
今日もニュースになっていましたね・・気を付けていらっしゃるでしょうけど
十分対策してくださいね。
>響さん
K君はセンス抜群です。
今回は本命を掘り当てて面目躍如でしたけど^^;
by ぜふ (2016-11-14 20:59)
Google Mapって便利ですよね。
ストリートビューで路面状況も判るし、気になった店が
あれば検索できるし(^^♪
by ごろすけ (2016-11-14 23:11)
エンマムシって初めて見ました。
ハンミョウは土の中で越冬するんですね~
どこに埋まっているか、どうやって見つけるんでしょう。
by Nyandam (2016-11-16 11:20)
調整池と言うのは,水を貯めたり抜いたりするのですね
グーグルもそこまで最新ではないから、、、
南房総のあたたかな様子が、羨ましい季節になってきました
いよいよ越冬に入る虫さん達かな
by engrid (2016-11-16 17:51)
おはようございます^^
再びお邪魔しま~~~す♪
昨日、近くの公園へ皇帝ダリアの撮影に行って、偶然蝶を見つけました。まだいるのですね~やはり千葉って暖かいのかなぁ~
by mimimomo (2016-11-17 09:19)
こんばんは。
ホソミオツネントンボというのは越冬するんですか(@_@;)
どんなところでどうやって越冬するのでしょう。
お城の帰りにムラサキシジミを見ましたが、羽を広げてくれませんでした。残念 !
by yakko (2016-11-17 21:10)
赤銅色の、金属的な光沢が美しいですね。
土の中から掘り出すところが、宝探しのようです^^;。
冬眠中?
by sakamono (2016-11-17 23:47)
>ごろすけさん
便利すぎて、しかもタダというのがおそろしいです^^;
>Nyandamさん
集団で潜っています。
どこにいるかは、土の様子でわかります・・といいたいところですが・・^^;
>engridさん
マップ上では存在するのに行ってみるとない道もありますね。
南房総はあたたかくて虫たちも棲みやすいと思います♪
>mimimomoさん
どんなチョウでしたか~?
成虫越冬するチョウは色々いますので、その子たちでしょうかね。
>yakkoさん
林の中、藪の中で雨風をしのいでいると思いますが、とにかくじっとしていると思います。
ムラサキシジミも成虫越冬しますね♪
>sakamonoさん
そう、この金属光沢がたまらないのです^^
冬眠中のところを起こしているのです^^;
by ぜふ (2016-11-19 12:32)