"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。
イモコレゲーム [ファーブル会]
5月3日、GWのど真ん中、ファーブル会の観察・採集会の日でした。
チバから2時間あまりかけてサイタマの飯能市へ。
駅からさらに(現金払いのみ可の)バスで20分。はじめての開催地へ着きました。

参加人数が多かったため、2班に分かれて出発しました。

参加者は皆、捕虫網を持っていますが、中には写真撮影専門の参加者も。

彼女が撮っているのは・・

先日の記事でも登場した蛾ですが、ここではオスがメスを探して群飛していました。
婚活中の彼らはなかなか止まってくれなかったのですが、置いてきぼり覚悟で粘って撮影しました。
次に見つけたのは、(後から考えてみると)この日の探虫を象徴するような虫でした。

すぐ飛んでいってしまったのでザンネンでしたが、このあとはハムシラッシュ(大げさ)になったのでした。

6ミリくらい。(この独特の翅の持ち主はフラッシュ・ディフューザーを使った写真をボツにする能力がありました)
そして扉の写真の子。

6~8ミリでかなり個体差がある。 ハムシ界トップの毛深さだが翅には光沢もあって美麗。
ちょっと話はそれますが、後日このハムシを昆虫館にミニ展示した日のこと。
ベビーカーに乗った小さな男の子を連れた若いお父さんが来館しました。
館内を見学している様子を見るとはなしに見ていたのですが、男の子のある一言におどろきました。
水棲昆虫の水槽の前で彼は、「これはゲンゴロウじゃない、ガムシ!」とパパに言ったのです。
ゲンゴロウとガムシの違いがわかるこんな小さい子がいるとはと感動して、思わず近づいて声をかけました。
「お子さんはいくつですか?」
「3才です。実は今日、誕生日なんです」
あまりの偶然もうれしくて、帰るときこのトビサルハムシを記念に差し上げました。
お礼を言うパパに 「猿飛ハムシではありませんよ」 と言おうとしたのですが何とか思いとどまりました。
(若いパパには何のことやらでしょうからね)
チビッコ昆虫博士はベビーカーに乗ってゆうゆうと帰って行きました。

陣笠ハムシも猿飛ハムシも何匹か観察できました。
その他、クロウリハムシやウリハムシ、ムナキルリハムシなどもいました。
実は採集対象の本命はアゲハチョウだったのですが、予想外の少なさでした。
甲虫も少なかったのですが、ちょっとめずらしいのが。

セマダラコガネに似ていますが一回り小さくて扁平。鞘翅が寸詰まりでおしりが見えているのが特徴。
カメムシも何種類か観察できましたが、シャッターを押したくなるのはこの子。

この子たちもフォトジェニック・カメムシ。

アイスが溶けたクリームソーダのような色合い・・おいしそうとは思いませんが。

休憩していると参加者の中学生?の男の子が採集した昆虫を持ってきて「これ何ですか?」と。
渡されたタッパーを覗いてみるとそれはクロカタビロオサムシでした。
カタビロオサムシはオサムシの仲間の中で極例外的に翅が退化していなくて”飛べる”オサムシなのです。
エゾカタビロオサムシよりもクロカタビロオサムシは希少。
このフィールドにいるという予備情報もなかったのでびっくりしました。
「うわ、これはいいね、おめでとう!」と称えてはおきましたが、心中穏やかではなくなっていました。
みんなでお昼を食べたあと、その子が「もっとオサムシ探したいです」とお願いされたのは渡りに船でした。
二人でオサムシのいそうな林の中の少し開けた場所へ登ってみました。
そしたら・・

見つけてしまいました。
もちろん家にお連れして、オサムシマンションに入居していただきました。

一旦解散したあと、補習としてイモムシの同定練習をしました。
今日観察・採集したイモムシをイモムシハンドブックという図鑑を使って同定する”イモコレゲーム”。
お弁当を食べていたら目の前を這っていたこの子は分かりやすかったのですが。

意外にも同定できたのは12~3種類中、3種類だけでした。
ミズイロオナガ以外にわかったのは、トンボエダシャクとオオシマカラスヨトウ。(写真なし)
見たことあるような気がするのですが・・ヒットしない。

これは前日、大町公園で観察したイモムシですが・・

30ミリ弱。ハンノキにいました。

少し大きい別のイモムシ。 同一種なのかもしれませんがさっぱり分かりません。

これは先日、裏高尾ではじめて観察した、かなり特徴的なイモムシ・・と呼んでいいと思いますが・・

威嚇しているのです。 コワイですね。ちゃんと驚いてあげましょう。

エダシャクの仲間の幼虫はみなこんな姿形をしているわけではありません。
逆に成虫になるとむしろ特徴がなくなる面白い蛾です。
そして最後に今日観察したイモムシを・・本人、ケムシではないと言っておりますので。

こちらは文句なしのイモムシ。 やっと今年花が咲くようになったミカンの木に。

葉っぱと全く同じ色で迷彩にはなっているのですが、あんまり天辺にいると鳥に見つかるよ・・

めんこくて癒されます。
先日のコヤマトンボにつつぎ、今日デビューしました。

こんな小さい(3センチほどの)ヤゴが・・

倍の大きさに。
胴体の色がまだ薄いです。
今日の湯加減
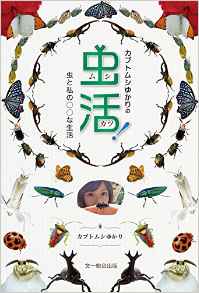
チバから2時間あまりかけてサイタマの飯能市へ。
駅からさらに(現金払いのみ可の)バスで20分。はじめての開催地へ着きました。

参加人数が多かったため、2班に分かれて出発しました。

参加者は皆、捕虫網を持っていますが、中には写真撮影専門の参加者も。

彼女が撮っているのは・・

クロハネシロヒゲナガ ♂ (ヒゲナガガ科)
先日の記事でも登場した蛾ですが、ここではオスがメスを探して群飛していました。
婚活中の彼らはなかなか止まってくれなかったのですが、置いてきぼり覚悟で粘って撮影しました。
次に見つけたのは、(後から考えてみると)この日の探虫を象徴するような虫でした。

ツツハムシの仲間
すぐ飛んでいってしまったのでザンネンでしたが、このあとはハムシラッシュ(大げさ)になったのでした。

セモンジンガサハムシ (ハムシ科)
6ミリくらい。(この独特の翅の持ち主はフラッシュ・ディフューザーを使った写真をボツにする能力がありました)
そして扉の写真の子。

トビサルハムシ (ハムシ科)
6~8ミリでかなり個体差がある。 ハムシ界トップの毛深さだが翅には光沢もあって美麗。
ちょっと話はそれますが、後日このハムシを昆虫館にミニ展示した日のこと。
ベビーカーに乗った小さな男の子を連れた若いお父さんが来館しました。
館内を見学している様子を見るとはなしに見ていたのですが、男の子のある一言におどろきました。
水棲昆虫の水槽の前で彼は、「これはゲンゴロウじゃない、ガムシ!」とパパに言ったのです。
ゲンゴロウとガムシの違いがわかるこんな小さい子がいるとはと感動して、思わず近づいて声をかけました。
「お子さんはいくつですか?」
「3才です。実は今日、誕生日なんです」
あまりの偶然もうれしくて、帰るときこのトビサルハムシを記念に差し上げました。
お礼を言うパパに 「猿飛ハムシではありませんよ」 と言おうとしたのですが何とか思いとどまりました。
(若いパパには何のことやらでしょうからね)
チビッコ昆虫博士はベビーカーに乗ってゆうゆうと帰って行きました。
陣笠ハムシも猿飛ハムシも何匹か観察できました。
その他、クロウリハムシやウリハムシ、ムナキルリハムシなどもいました。
実は採集対象の本命はアゲハチョウだったのですが、予想外の少なさでした。
甲虫も少なかったのですが、ちょっとめずらしいのが。

ヒラタハナムグリ (コガネムシ科)
セマダラコガネに似ていますが一回り小さくて扁平。鞘翅が寸詰まりでおしりが見えているのが特徴。
カメムシも何種類か観察できましたが、シャッターを押したくなるのはこの子。

エサキモンキツノカメムシ (ツノカメムシ科)
この子たちもフォトジェニック・カメムシ。

アイスが溶けたクリームソーダのような色合い・・おいしそうとは思いませんが。

ヘラクヌギカメムシの幼虫? (クヌギカメムシ科)
休憩していると参加者の中学生?の男の子が採集した昆虫を持ってきて「これ何ですか?」と。
渡されたタッパーを覗いてみるとそれはクロカタビロオサムシでした。
カタビロオサムシはオサムシの仲間の中で極例外的に翅が退化していなくて”飛べる”オサムシなのです。
エゾカタビロオサムシよりもクロカタビロオサムシは希少。
このフィールドにいるという予備情報もなかったのでびっくりしました。
「うわ、これはいいね、おめでとう!」と称えてはおきましたが、心中穏やかではなくなっていました。
みんなでお昼を食べたあと、その子が「もっとオサムシ探したいです」とお願いされたのは渡りに船でした。
二人でオサムシのいそうな林の中の少し開けた場所へ登ってみました。
そしたら・・

クロカタビロオサムシ (オサムシ科)
見つけてしまいました。
もちろん家にお連れして、オサムシマンションに入居していただきました。
一旦解散したあと、補習としてイモムシの同定練習をしました。
今日観察・採集したイモムシをイモムシハンドブックという図鑑を使って同定する”イモコレゲーム”。
お弁当を食べていたら目の前を這っていたこの子は分かりやすかったのですが。

ミズイロオナガシジミ 幼虫 (ミドリシジミ科)
意外にも同定できたのは12~3種類中、3種類だけでした。
ミズイロオナガ以外にわかったのは、トンボエダシャクとオオシマカラスヨトウ。(写真なし)
見たことあるような気がするのですが・・ヒットしない。

これは前日、大町公園で観察したイモムシですが・・

30ミリ弱。ハンノキにいました。

少し大きい別のイモムシ。 同一種なのかもしれませんがさっぱり分かりません。
これは先日、裏高尾ではじめて観察した、かなり特徴的なイモムシ・・と呼んでいいと思いますが・・

クロモンキリバエダシャク 幼虫 (シャクガ科)
威嚇しているのです。 コワイですね。ちゃんと驚いてあげましょう。

エダシャクの仲間の幼虫はみなこんな姿形をしているわけではありません。
逆に成虫になるとむしろ特徴がなくなる面白い蛾です。
そして最後に今日観察したイモムシを・・本人、ケムシではないと言っておりますので。

ルリタテハ 幼虫 (タテハチョウ科)
こちらは文句なしのイモムシ。 やっと今年花が咲くようになったミカンの木に。

アゲハの幼虫 (アゲハチョウ科)
葉っぱと全く同じ色で迷彩にはなっているのですが、あんまり天辺にいると鳥に見つかるよ・・

柚子坊(ゆずぼう)ともいいます
めんこくて癒されます。
オマケ
先日のコヤマトンボにつつぎ、今日デビューしました。

こんな小さい(3センチほどの)ヤゴが・・

ハグロトンボ ♀ (カワトンボ科)
倍の大きさに。
胴体の色がまだ薄いです。
今日の湯加減
今日は探虫というよりも虫のエサを求めてあちこち駆け回りました。
ジャコウアゲハの幼虫のためのウマノスズクサ。
クヌギ、コナラ、イタドリ、カタツムリ、そしてセンチコガネ用の○○○。
シロシタホタルガの幼虫のためのサワフタギは見つけられませんでした。
こちらは全国書店かアマゾンで見つけられると思います。
「カブトムシゆかりの虫活 ~虫と私の○○な関係~」
拙ブログの写真も何枚か使ってもらっています。
立ち読みだけでもぜひ。
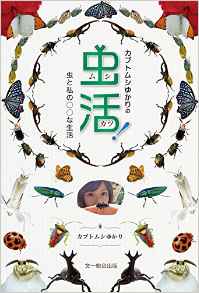
"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。





この中ではっきり解るのはアゲハの幼虫くらいでしょうか
たくさん見れば見るほど混乱してます。
by g_g (2016-05-29 08:05)
うおぉぉ~~
恐るおそる拝見しました~~~^^;
ブルブル・・・
by よしころん (2016-05-29 08:45)
このイモムシの形から、あのアゲハになるのって、
分かってはいますが、未だに信じられないほど不思議な事です(^_^;)
それにしても3歳の昆虫博士、すごいなぁ。
by sasasa (2016-05-29 21:05)
アゲハの幼虫、本当にめんこいですね。
ルリタテハのこの棘は、刺されても大丈夫なのでしょうか。
イラガの幼虫に似ているようですが、こちらは刺されるとひりひりしてしばらく酷い目に会います。
by アヨアン・イゴカー (2016-05-29 23:04)
こんにちは^^
お花がたくさんあると同じように、虫もたくさんですね~
綺麗なお色のもあるし、なんだかトゲトゲが痛そうなのも^^
アゲハの幼虫はしっていますし、ルリタテハも我が家ではおなじみです。
by mimimomo (2016-05-30 09:58)
チビッコ昆虫博士、将来が楽しみですねー^^
アゲハの幼虫、おもしろい顔してる。
なんか可愛らしいですね。
by リュカ (2016-05-30 13:24)
こんにちは。
三歳の虫博士 ! 将来が楽しみですね〜〜〜
by yakko (2016-05-30 13:48)
たくさんの虫たち
それぞれに自己主張の個体差、、自然界恐るべしです
アゲハの幼虫くん、私もすでにの遭遇
あのトボケタような顔を見ると つい笑ってしまいます
憎めない、、山椒の葉を食べ尽くさないように、願うばかりです
by engrid (2016-05-31 18:14)
ルリタテハのイモ虫さんファンキーですね
本当にどの子もみな神の賜物
感動してしまいました^^
by shino* (2016-05-31 21:02)
>g_gさん
イモムシの同定は想像をはるかに超えていました。
ゆずぼうはすぐわかりますが^^
>よしころんさん
あれ?だめでしたか? 意外です。
花撮影されていたら出くわすこともあるでしょうに^^
>sasasaさん
イモムシに限らず・・ですね。
ゲンゴロウとガムシの違い、わかりますか?^^
>アヨアン・イゴカーさん
ルリタテハは触っても大丈夫ですが、イラガの幼虫はキケンですよね^^;
めんこいゆずぼう・・次の日、いなくなってました・・><
>mimimomoさん
このところイモムシにハマっています^^;
ルリタテハがおなじみなのはホトトギスがあるからですか?^^
>リュカさん
彼とはいつか再会したいです♪
ゆずぼう、きっと見ているのは”顔”ではないのでは?^^
>yakkoさん
お父さんもすばらしいと思いました!^^
>engridさん
山椒があれば他のアゲハも来そうですね♪
アゲハたちに代わっておわび申し上げます^^;
>shino*さん
ルリタテハは線香花火みたいではじけてるでしょ?^^
ほんとにこういう子に出会うとほっとします。 うれしかったー♪
by ぜふ (2016-05-31 22:50)
ルリタテハの幼虫、こんな姿なんですね!
かっこいい!
by ligia (2016-06-01 20:58)
今日はハムシ祭りかと思ったら
いっぱい見つけましたね。
ルリタテハの幼虫はもう地球外生命です。
by 響 (2016-06-02 13:03)
「続きを読む」を押すのを、ちょっとためらいましたが、こんな感じの
小さなイモムシならダイジョブでした^^;。
セモンジンガサハムシ、面白い形ですねー。
by sakamono (2016-06-02 23:35)
飛び去るハムシと思ったんですが猿飛ハムシ(笑)
もう忘れません(^^)v
by barbie (2016-06-03 12:45)
>ligiaさん
いろいろなモチーフになりえると思います。
筆にも?^^
>響さん
ルリちゃんの造形美は地球人の許容を超えているかもですね♪
実は次記事、ハムシ祭りです^^;
>sakamonoさん
この子たちが大丈夫なら、もう大丈夫ですよ^^
ジンガサハムシはこれでしかも飛べるというのがさらに面白いです♪
>barbieさん
それは本名ではないのでよろしくお願いします^^;
あ、でも猿飛がわかるんですね・・^^
by ぜふ (2016-06-04 07:37)