"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。
千虫万来 [ファーブル会]
採集会の解散後はいつもスタッフ何人かで残業採集をします。
7月15日も近くのポイントへ移動し残業しましたが、まったくと言っていいほど収獲なし。
プチ熱中症のため粘る気力もなし。
ということで撤収・・・とはならず、なぜかナイター&野宿ということに。
でもその前に道の駅にらさきのスパへ行き、お風呂に入って汗を流し、休憩しつつ水分補給しました。
それからスーパーへ買い出しに。
水と食料と燃料(ビール)を仕入れ、車2台で山を目指しました。
ポイントに着き、さっそくライトトラップを設営したらちょうど日没。

空はまだ明るいのに、ライトを点灯すると、すぐに何か飛んできました。

15ミリほどしかないのでゴミムシだと思いましたが、ずいぶんキバが発達しているなぁと・・
ゴミムシではなくクロカミキリでした。
ポケット図鑑で調べると体長は11.5~23ミリとずいぶん幅があることを認識。
その後もたくさんやってきました。

辺りが暗くなると蛾もやってきます。
目立った子だけ紹介していきます。
幅が10センチ近くある大きな子。

甲虫類もぞくぞくやってきます。
5ミリくらいのちっちゃい子。

コガネムシたちも。
これは”ザ・コガネムシ”だと思います。

体色は個体変異があってさまざまですが、光の当たり方によっても変わってしまいます。
この写真の方がコガネムシらしいでしょうか。


ひときわ大きな甲虫も飛んできました。

4センチ以上にもなる国内最大のシデムシ。
大きくて真ん丸の目も特徴。(アップも撮ったのですが被写体ブレばかりでした)

ブラックライトの紫外線に誘引されるのか、こんな虫たちもやってきます。

飛んできたセミはこの一種だけでした。

灯火に誘引されるカメムシもいます。
この子は色合いといい、柄といい、形といい、かなりの美麗種。

この子も形がカッコイイ。

ハサミがあるのはオスだけ。

8時を過ぎると蛾がラッシュしてきました。
観察しながらおしゃべりすると口の中に飛び込んできてしまうほど。

先日、科博のリレートークショーで国内の蛾の種数が6千という話を聞きましたが、
(ずっと4千種だと思っていましたが増えたのでしょう)
たしかに一か所にこれだけいるのであれば、さもありなんと思いました。
多分これだけで何百種といると思うので、とてもすべてを撮影することはできません。
目に付いた子だけ厳選して紹介します。
ドット柄が爽やかな細身の子。

歌舞伎の隈取りのような柄の子。複数きました。

シースルーの紋付の子。

黄色い子。

青い子その1。40ミリくらい。

青い子その2。50ミリくらい。

翅の縁がチョウのように波打っていて開き方もタテハチョウのようでした。

この子たちがやってくるとやはり盛り上がります。

この子も中歯型。


翌日撮影した写真ですが、大歯型も来ました。

メスも。


深夜を過ぎてもまだまだ蛾の飛来は引きも切らず。
観察している人たちのシャツの胸や背中や頭にも多数とまり、それを観察したり。
ヤママユの仲間が来てくれなかったのがザンネンでしたが、カマキリモドキやヘビトンボが来たり。
(後記:ヤママユの発生時期は9月くらいからなので来ないのは当たり前)
あ、ミミズクも来ました。
鳥ではないです。
逃げられては困るのですぐ確保したためゆっくり撮影できず。証拠写真のみ。

そういえば糞虫はまったく来ませんでした。
なぜかツユムシが何匹もやってきたのですが、彼らは灯火よりもこっちに寄ってきました。

山の夜の宴会は2時頃まで続きました。(燃料が切れてライトが消えたところで終了)
翌朝、車の中で目が覚める。
一番大事な収獲であるミヤマクワガタの安否を確認しようとカバンの中からケースを出すと・・
いない。
ゆるく締まるタッパだったのでビニールテープでとめていたのですが甘かったようでした。
二度寝をしてもう一度目が覚めたらフロアマットの上に佇むメスを発見。
シートの下や荷物スペースなどを探すも、どこかのスキマに入ったのか、オスは結局見つからず。
・・・帰宅後、連れて帰ったメスのお家をさっそくセッティング。
産卵木も埋めて出来上がり。

クヌギのマットにまみれて気持ちよさそうでした。

今日の湯加減
7月15日も近くのポイントへ移動し残業しましたが、まったくと言っていいほど収獲なし。
プチ熱中症のため粘る気力もなし。
ということで撤収・・・とはならず、なぜかナイター&野宿ということに。
でもその前に道の駅にらさきのスパへ行き、お風呂に入って汗を流し、休憩しつつ水分補給しました。
それからスーパーへ買い出しに。
水と食料と燃料(ビール)を仕入れ、車2台で山を目指しました。
ポイントに着き、さっそくライトトラップを設営したらちょうど日没。

空はまだ明るいのに、ライトを点灯すると、すぐに何か飛んできました。

クロカミキリ (カミキリムシ科)
15ミリほどしかないのでゴミムシだと思いましたが、ずいぶんキバが発達しているなぁと・・
ゴミムシではなくクロカミキリでした。
ポケット図鑑で調べると体長は11.5~23ミリとずいぶん幅があることを認識。
その後もたくさんやってきました。

辺りが暗くなると蛾もやってきます。
目立った子だけ紹介していきます。
幅が10センチ近くある大きな子。

クチバスズメ (スズメガ科)
甲虫類もぞくぞくやってきます。
5ミリくらいのちっちゃい子。

シロトホシテントウ (テントウムシ科)
コガネムシたちも。
これは”ザ・コガネムシ”だと思います。

コガネムシ (コガネムシ科)
体色は個体変異があってさまざまですが、光の当たり方によっても変わってしまいます。
この写真の方がコガネムシらしいでしょうか。

同上
ひときわ大きな甲虫も飛んできました。

クロシデムシ (シデムシ科)
4センチ以上にもなる国内最大のシデムシ。
大きくて真ん丸の目も特徴。(アップも撮ったのですが被写体ブレばかりでした)
ブラックライトの紫外線に誘引されるのか、こんな虫たちもやってきます。

エゾハルゼミ ♀ (セミ科)
飛んできたセミはこの一種だけでした。

同上
灯火に誘引されるカメムシもいます。
この子は色合いといい、柄といい、形といい、かなりの美麗種。

ツノアオカメムシ (カメムシ科)
この子も形がカッコイイ。

ハサミツノカメムシ ♂ (カメムシ科)
ハサミがあるのはオスだけ。
8時を過ぎると蛾がラッシュしてきました。
観察しながらおしゃべりすると口の中に飛び込んできてしまうほど。

先日、科博のリレートークショーで国内の蛾の種数が6千という話を聞きましたが、
(ずっと4千種だと思っていましたが増えたのでしょう)
たしかに一か所にこれだけいるのであれば、さもありなんと思いました。
多分これだけで何百種といると思うので、とてもすべてを撮影することはできません。
目に付いた子だけ厳選して紹介します。
ドット柄が爽やかな細身の子。

ニシキギスガ (スガ科)
歌舞伎の隈取りのような柄の子。複数きました。

アカスジシロコケガ (ヒトリガ科)
シースルーの紋付の子。

ヒトツメオオシロヒメシャク (シャクガ科)
黄色い子。

キシタバ (ヤガ科)
青い子その1。40ミリくらい。

カギシロスジアオシャク (シャクガ科)
青い子その2。50ミリくらい。

クロスジアオシャク (シャクガ科)
翅の縁がチョウのように波打っていて開き方もタテハチョウのようでした。
この子たちがやってくるとやはり盛り上がります。

アカアシクワガタ (クワガタムシ科)
この子も中歯型。

ミヤマクワガタ (クワガタムシ科)

同上
翌日撮影した写真ですが、大歯型も来ました。

同上
メスも。

同上
深夜を過ぎてもまだまだ蛾の飛来は引きも切らず。
観察している人たちのシャツの胸や背中や頭にも多数とまり、それを観察したり。
ヤママユの仲間が来てくれなかったのがザンネンでしたが、カマキリモドキやヘビトンボが来たり。
(後記:ヤママユの発生時期は9月くらいからなので来ないのは当たり前)
あ、ミミズクも来ました。
鳥ではないです。
逃げられては困るのですぐ確保したためゆっくり撮影できず。証拠写真のみ。

ミミズク (ヨコバイ科)
そういえば糞虫はまったく来ませんでした。
なぜかツユムシが何匹もやってきたのですが、彼らは灯火よりもこっちに寄ってきました。

山の夜の宴会は2時頃まで続きました。(燃料が切れてライトが消えたところで終了)
オマケ
翌朝、車の中で目が覚める。
一番大事な収獲であるミヤマクワガタの安否を確認しようとカバンの中からケースを出すと・・
いない。
ゆるく締まるタッパだったのでビニールテープでとめていたのですが甘かったようでした。
二度寝をしてもう一度目が覚めたらフロアマットの上に佇むメスを発見。
シートの下や荷物スペースなどを探すも、どこかのスキマに入ったのか、オスは結局見つからず。
・・・帰宅後、連れて帰ったメスのお家をさっそくセッティング。
産卵木も埋めて出来上がり。

クヌギのマットにまみれて気持ちよさそうでした。

今日の湯加減
台風12号(ジョンダリ)が本州に向かってきています。
日本列島に近づいてくる台風の進路はたいていはシュートして北東方向へ向かいます。
ところがジョンダリは小笠原諸島を過ぎたあたりからシュートではなく、フックして北西方向へ。
天気予報では台風の進路を予報円で表示しますが、予報円の南西端を辿り、むしろ真西に向かいそう。
2日前は関東直撃と思われたのが東海地方上陸に変わり、さらに近畿地方上陸の予想になりました。
このままでは西日本を横断していくことになり、先日の被災地が心配になってきます。
勢力が弱まることを願うばかり。
今日から明日にかけて予定されていたファーブル会の一泊採集会も中止になりました。
参加予定だったゲストはがっかりだと思いますが、スタッフも楽しみにしていたのでザンネンです。
というわけで今日はブログ&標本日和でした。
8月1日は奥本先生とカブちゃんのトークショーもあります!
"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。
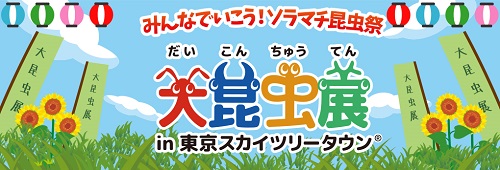





まさに千客万来ですね。
ミヤマさん会いたい!
これに合いに山に行ったけどコガネムシしか会えませんでした。
by 響 (2018-07-29 10:38)
光によってグリーンに輝く、同じコガネムシとは思えませんね。
蛾はかぶれたことがあるのでパスしたいです(笑)
by barbie (2018-07-29 15:55)
クヌギのマット、やわらかくて
本当に気持ちよさそう^^
あー、観ていたら欲しくなるwww
かわいいなーかわいいなーーーー
by リュカ (2018-07-30 10:34)
>響さん
そちらだと相当標高を上げないと見つからないかもしれませんね。
コガネムシも多種多彩でおもしろいです!^^
>barbieさん
コガネムシは玉虫色なんですよねー^^
蛾の成虫はほとんど害がないと思います。
>リュカさん
世話していると馴れてくれますからね♪
ぜひミヤママを^^
by ぜふ (2018-07-31 22:27)
おはようございます^^
凄い種類!
ハサミツノカメムシ、これはわたくしが一等賞を与えます^^
綺麗だもの~♪
蛾は綺麗でも何となくあまり好きになれませんが(へへゞ
by mimimomo (2018-08-01 07:34)
野宿って、どうするのかと思ったら、車中泊でしたか^^;。
蛾なんて、あまり意識したコトがありませんでしたが、
種類によって、いろんな色や形で、キレイですね。
薄茶色っぽいイメージばかりで^^;。
それと「ザ・コガネムシ」の写真!
これだとまさにコガネ色ですね。こんなふうな色に
見えたコトがありません。
by sakamono (2018-08-02 22:33)
>mimimomoさん
ハサミツノカメムシがお気に入るとは意外でした(笑)
カッコイイし機能美がありますね♪
>sakamonoさん
美しい蛾は多いですね。色は地味でも、柄や形が美しい種類も。
コガネムシは実は同定がとても難しいです^^;
by ぜふ (2018-08-02 22:50)