"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。
メロンソーダの季節 [ゼフィルス]
6月になり、さすがに気になって我慢できなくなり、HFへ行ってきました。
今年は季節が早いのでおそらくもう出ていて、さらにはもうピークを迎えているかもしれない。
そうあらためて想像すると気持ちが急いてきました。
が、どういうわけかナラのときとは違って寝坊する始末。

結果的には会えたのでよかったけれど。
午後から先生の講演と総会のために出かけるのですが、今回はお手伝いもできないので準備もなし。
ただしかし、前日夜に寝落ちしたため、ある昆虫を準備するのを忘れているのに気付く。
OBC(秘密指令のコードネーム)のためにせっせと虫を選定してケースに格納しました。
そんなことをしている内にさらに時間は経ち、7時になってしまいました。
あわててカメラを担ぎ、ベニシジミ号のエンジンをかけて出発。
いつもは使わない高速道路に乗りました。

おかげで約20分後には谷津田の入口に到着。
急いでハンノキ林へ。絶好の観察ポイントの木へ一直線。
目を凝らして上から下までチェックしていると目の前にこの子がいました。

朝ごはん中でしたが、食べ方までゴマダラでした。(ヒョウ柄ともいう?)
ともかく、ハンノキも食べるということがわかりました。
さて、肝心の子は見つからず、さらに林の奥へ入り、下草の上を丹念に見回りましたがいません。
イナゴライダーたちはたくさんいました。

場所を変えることにしました。

林を出て一旦入口まで戻り、林縁の様子を確認しながら散策路をゆっくり歩いていると。
ある意味指標虫を観察できました。

ゼフの季節に現れる虫ですが、そういえばこの日はじめて見つけました。
ということは、HFではまだシーズンははじまったばかりと言えるかもしれないと安心。
と、その時、コンチューターの針がいきなり振り切れました。
脊髄反射で立ち止まり、直立不動のまま目線だけで辺りをうかがうと、ほんの一歩先の散策路上の雑草の葉にお目当ての子がいたのです。
しかも、2頭も。
しかも、1頭は翅を半開きにしてゼフィルスビームを発射しているではないですか。
慌てつつも息を殺し、ウエストバッグからカメラを取り出して電源オン。
モードをセレクトして予めズーミングもし、膝を曲げて体勢を低くしつつレンズを向け、シャッターを切ろうとした瞬間。
1頭が飛び立ち、それにつられてもう1頭も舞い上がってしまいました。
証拠写真すら撮らせてもらえなくてがっかり。
遅刻したこともあり、これはひょっとしたら本日唯一のチャンスを逃したかもしれないと天を仰ぐと・・

羽化したてでしょうか、翅がセロファンのようにキラキラと陽光を反射していました。

もう一度、ハンノキ林に今度は反対側から入ってみることにしました。
今年は林の中の小流もきれいに浚渫され、両側の雑草も刈られてとても歩きやすくなっています。
観察するのにはとても好都合なのですが、虫たちの生態に対してはどうなのでしょう。
この子はあまり気にしていない様子。

ゼフたちはやはりもう梢の上に移動してしまったのでしょうか、見つかりませんでした。
田んぼに戻ると、観察会の下見に来た観察指導員の方たちのお出まし。
聞くと今日はカエルがテーマとのことでした。
参加されますかと尋ねられましたが、時間がないので自由行動しますとお断り。

帰ることを考えながらぼんやり歩いていると、20メートルほど前方に何かが舞い降りました。
落ち葉かもしれないけれど、今度はカメラバッグから一眼レフを出しつつゆっくり近づいていきます。
目視できる距離まできた時、それは落ち葉ではないことが分かりました。
しかもフルオープン。
そのままそのままと祈りながらにじり寄り、ピントを合わせてシャッターを切ろうとした瞬間。
「おはようございまーす」
と背後から声をかけられました。
知り合いではありませんが、谷津田のゴミ拾いなどをしてくれているボランティアの二人でした。
中腰で下を向いてカメラを構えた姿勢のまま、返事することができません。
被写体も気配を察知して翅を閉じてしまいました。
失礼だとは思いつつ、そのまま二人をやり過ごし、ファインダーを覗きながら「開け~開け~」と念じていると・・
バックアングルなので全面グリーンには光らないのですが、開いてくれました。

さらにさっき歩いてきた散策路でも。
立て続けで動揺が収まりきらないままだったためかピンアマになりましたが証拠写真として。

そして扉の写真の子のフルオープンの様子。

今年も逢えてよかった。メロンソーダくん。
メスは見かけなかったのでピークはこれからでしょう。

一応ボウズは免れたので、HFの他の場所の様子も見ようと、入口に向けて歩いていきました。
こんな杉林の中を進みます。

地表にはやたらとザトウムシの姿が目に付くのですが、これははじめて見ました。

だと思いますがここでははじめて見ました。
この虫も極普通種ですが、ここでははじめてかもしれません。

この谷津田は花が多くないので、チョウやハナムグリやハチも少ないのです。

まだ少し時間があるので田んぼに戻り、誰か降りてくるのを待つ作戦に変更。
あぜ道の一角、陽射しも強くなってきたので日陰になるところででじっと佇んでいると、
また一頭舞い降りてきてくれました。

オオバコの葉には陽が当たっていたので開いてくれるかなと思いましたがぴょんと飛び降り。
地面の上へと。

目的はミネラル補給。
夢中になってちゅうちゅうしているときは、いくら近寄っても大丈夫です。

アゲハやタテハチョウの仲間はよくこうして地面に降りてきます。
シジミチョウの仲間だと、ルリシジミは集団吸水することが知られています。
ミドリシジミも同様の行動生態があるということでしょう。
でも、このあと、こんな子もこのすぐ近くに舞い降りたのです。

そして水路の畔で吸水。

ここは何か特別な成分のホットスポットなのかもしれません。
研究対象にできるかも。

そうこうしている内に観察会開始時刻になり、参加者たちがぞろぞろと田んぼにやってきました。
せっかくなので顔見知りの観察指導員さんたちに軽く挨拶だけして撤収モードに。
するとまた目の前に何か小さなものがふわりと舞い降りました。
一瞬見失いましたが、葉の裏へ逃げるのを見逃しませんでした。

この日はHF初物ラッシュのようです。普通種ですが他のフィールドでもたまにしか見ません。
これは初物ではありませんが、ベニシジミ号に戻りつつも林縁をチェックしていると。

終齢かもしれませんが、まだ幼虫。
ベニシジミ号までたどり着き、帰り支度をしていると目の前の木の幹に初物。

そしてまさにヘルメットをかぶろうとしたとき、また何か上から降ってきました。
飛ぶのが得意ではなくて、降ってきたというか、ふわふわと落ちてきたという感じでした。

一度にこんなに多種のカミキリムシをHFで見たのははじめてでした。
さあ急いで帰らなくちゃ。
前記事の続きで、あらためてルリセンチを紹介します。

こちらは通常色のオオセンチコガネ。

どうしてこんなに色彩変異があるのでしょうか。
ナラはルリセンチが多いですが、ミドリセンチも少数観察できる一方、通常色はいません。
通常色が主に生息する九州のとある場所でもミドリセンチが少数いるそうです。
でもルリセンチがいるのは紀伊半島の一部のみ。
何か環境因子もあるのでしょうか。
これも間違いなく研究対象になります。
今日の湯加減
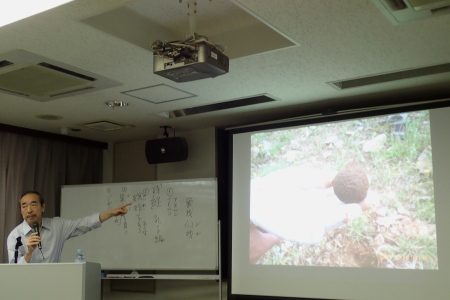
今年は季節が早いのでおそらくもう出ていて、さらにはもうピークを迎えているかもしれない。
そうあらためて想像すると気持ちが急いてきました。
が、どういうわけかナラのときとは違って寝坊する始末。

結果的には会えたのでよかったけれど。
午後から先生の講演と総会のために出かけるのですが、今回はお手伝いもできないので準備もなし。
ただしかし、前日夜に寝落ちしたため、ある昆虫を準備するのを忘れているのに気付く。
OBC(秘密指令のコードネーム)のためにせっせと虫を選定してケースに格納しました。
そんなことをしている内にさらに時間は経ち、7時になってしまいました。
あわててカメラを担ぎ、ベニシジミ号のエンジンをかけて出発。
いつもは使わない高速道路に乗りました。
おかげで約20分後には谷津田の入口に到着。
急いでハンノキ林へ。絶好の観察ポイントの木へ一直線。
目を凝らして上から下までチェックしていると目の前にこの子がいました。

ゴマダラオトシブミ (オトシブミ科)
朝ごはん中でしたが、食べ方までゴマダラでした。(ヒョウ柄ともいう?)
ともかく、ハンノキも食べるということがわかりました。
さて、肝心の子は見つからず、さらに林の奥へ入り、下草の上を丹念に見回りましたがいません。
イナゴライダーたちはたくさんいました。

コバネイナゴの幼虫 (バッタ科)
場所を変えることにしました。
林を出て一旦入口まで戻り、林縁の様子を確認しながら散策路をゆっくり歩いていると。
ある意味指標虫を観察できました。

カノコガ (ヒトリガ科)
ゼフの季節に現れる虫ですが、そういえばこの日はじめて見つけました。
ということは、HFではまだシーズンははじまったばかりと言えるかもしれないと安心。
と、その時、コンチューターの針がいきなり振り切れました。
脊髄反射で立ち止まり、直立不動のまま目線だけで辺りをうかがうと、ほんの一歩先の散策路上の雑草の葉にお目当ての子がいたのです。
しかも、2頭も。
しかも、1頭は翅を半開きにしてゼフィルスビームを発射しているではないですか。
慌てつつも息を殺し、ウエストバッグからカメラを取り出して電源オン。
モードをセレクトして予めズーミングもし、膝を曲げて体勢を低くしつつレンズを向け、シャッターを切ろうとした瞬間。
1頭が飛び立ち、それにつられてもう1頭も舞い上がってしまいました。
証拠写真すら撮らせてもらえなくてがっかり。
遅刻したこともあり、これはひょっとしたら本日唯一のチャンスを逃したかもしれないと天を仰ぐと・・

オオシオカラトンボ ♀ (トンボ科)
羽化したてでしょうか、翅がセロファンのようにキラキラと陽光を反射していました。
もう一度、ハンノキ林に今度は反対側から入ってみることにしました。
今年は林の中の小流もきれいに浚渫され、両側の雑草も刈られてとても歩きやすくなっています。
観察するのにはとても好都合なのですが、虫たちの生態に対してはどうなのでしょう。
この子はあまり気にしていない様子。

ニホンアカガエル
ゼフたちはやはりもう梢の上に移動してしまったのでしょうか、見つかりませんでした。
田んぼに戻ると、観察会の下見に来た観察指導員の方たちのお出まし。
聞くと今日はカエルがテーマとのことでした。
参加されますかと尋ねられましたが、時間がないので自由行動しますとお断り。

帰ることを考えながらぼんやり歩いていると、20メートルほど前方に何かが舞い降りました。
落ち葉かもしれないけれど、今度はカメラバッグから一眼レフを出しつつゆっくり近づいていきます。
目視できる距離まできた時、それは落ち葉ではないことが分かりました。
しかもフルオープン。
そのままそのままと祈りながらにじり寄り、ピントを合わせてシャッターを切ろうとした瞬間。
「おはようございまーす」
と背後から声をかけられました。
知り合いではありませんが、谷津田のゴミ拾いなどをしてくれているボランティアの二人でした。
中腰で下を向いてカメラを構えた姿勢のまま、返事することができません。
被写体も気配を察知して翅を閉じてしまいました。
失礼だとは思いつつ、そのまま二人をやり過ごし、ファインダーを覗きながら「開け~開け~」と念じていると・・
バックアングルなので全面グリーンには光らないのですが、開いてくれました。

ミドリシジミ ♂ (シジミチョウ科)
さらにさっき歩いてきた散策路でも。
立て続けで動揺が収まりきらないままだったためかピンアマになりましたが証拠写真として。

同上
そして扉の写真の子のフルオープンの様子。

同上
今年も逢えてよかった。メロンソーダくん。
メスは見かけなかったのでピークはこれからでしょう。
一応ボウズは免れたので、HFの他の場所の様子も見ようと、入口に向けて歩いていきました。
こんな杉林の中を進みます。

地表にはやたらとザトウムシの姿が目に付くのですが、これははじめて見ました。

コクロナガオサムシ の死骸(オサムシ科)
だと思いますがここでははじめて見ました。
この虫も極普通種ですが、ここでははじめてかもしれません。

ヨツスジハナカミキリ (カミキリムシ科)
この谷津田は花が多くないので、チョウやハナムグリやハチも少ないのです。
まだ少し時間があるので田んぼに戻り、誰か降りてくるのを待つ作戦に変更。
あぜ道の一角、陽射しも強くなってきたので日陰になるところででじっと佇んでいると、
また一頭舞い降りてきてくれました。

オオバコの葉には陽が当たっていたので開いてくれるかなと思いましたがぴょんと飛び降り。
地面の上へと。

目的はミネラル補給。
夢中になってちゅうちゅうしているときは、いくら近寄っても大丈夫です。

アゲハやタテハチョウの仲間はよくこうして地面に降りてきます。
シジミチョウの仲間だと、ルリシジミは集団吸水することが知られています。
ミドリシジミも同様の行動生態があるということでしょう。
でも、このあと、こんな子もこのすぐ近くに舞い降りたのです。

スジグロシロチョウ (シロチョウ科)
そして水路の畔で吸水。

ここは何か特別な成分のホットスポットなのかもしれません。
研究対象にできるかも。
そうこうしている内に観察会開始時刻になり、参加者たちがぞろぞろと田んぼにやってきました。
せっかくなので顔見知りの観察指導員さんたちに軽く挨拶だけして撤収モードに。
するとまた目の前に何か小さなものがふわりと舞い降りました。
一瞬見失いましたが、葉の裏へ逃げるのを見逃しませんでした。

ヨツボシハムシ (ハムシ科)
この日はHF初物ラッシュのようです。普通種ですが他のフィールドでもたまにしか見ません。
これは初物ではありませんが、ベニシジミ号に戻りつつも林縁をチェックしていると。

ナナフシ (ナナフシ科)
終齢かもしれませんが、まだ幼虫。
ベニシジミ号までたどり着き、帰り支度をしていると目の前の木の幹に初物。

ヤハズカミキリ (カミキリムシ科)
そしてまさにヘルメットをかぶろうとしたとき、また何か上から降ってきました。
飛ぶのが得意ではなくて、降ってきたというか、ふわふわと落ちてきたという感じでした。

ベニカミキリ (カミキリムシ科)
一度にこんなに多種のカミキリムシをHFで見たのははじめてでした。
さあ急いで帰らなくちゃ。
オマケ
前記事の続きで、あらためてルリセンチを紹介します。

こちらは通常色のオオセンチコガネ。

どうしてこんなに色彩変異があるのでしょうか。
ナラはルリセンチが多いですが、ミドリセンチも少数観察できる一方、通常色はいません。
通常色が主に生息する九州のとある場所でもミドリセンチが少数いるそうです。
でもルリセンチがいるのは紀伊半島の一部のみ。
何か環境因子もあるのでしょうか。
これも間違いなく研究対象になります。
今日の湯加減
今年もHFでミドリシジミを観察することができてほっとしました。
ピークはまだこれからのようですが、今シーズンはもう撮影に行けないかもしれません。
スッタモンダの件は出口が見えてきたため、来週引越をします。
ということで、ドタバタのピークもまだこれから。
少しの間ブログお休みします。
記事の日の午後の先生の講演会はいい気分転換になりました。
そのあとの反省会も。
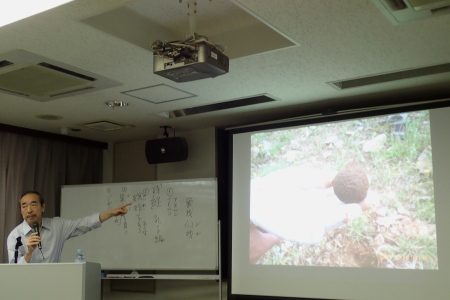
"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。





カメラを構えて微動だにぜず!こんな人には声かけたらあきませんね(笑)
ちゃんと撮れてよかったですね。
by barbie (2018-06-10 10:04)
記事タイトルの「メロンソーダ」とは何か? と思いながら
記事を読みました。なるほど、メロンソーダのようなあざやかな
色ですね。オオシオカラトンボの翅もキレですが、最後の
ルリセンチとオオセンチコガネの美しさにやられました。
by sakamono (2018-06-14 21:23)
>barbieさん
やな感じの人に思われたかもしれないので踏んだり蹴ったり^^;
いい子が現れてくれて助かりました。
>sakamonoさん
今回のメロンソーダはちょっと気が抜けてしまいました^^;
オオセンチたちの色は虫好きではなくても気に入ると思います。
by ぜふ (2018-06-15 22:13)
ぜふさん、こんにちは。
少し落ち着いてこられましたか^^
不明のトンボ画像を載せておりまして…
お時間あるときにブログ覗いていただければありがたいですm(_ _)m
by よしころん (2018-06-21 17:52)
>よしころんさん
拝見しました。サナエトンボの同定はむずかしいですが、
ダビドサナエのメスじゃないかなと思います。
前脚の基部が黄色だったら間違いないのですが。
by ぜふ (2018-06-23 00:32)
ぜふさん、おはようございます。
元画像確認したところ前脚の基部が黄色でした!
ダビドサナエのメス、ありがとうございます^^
by よしころん (2018-06-24 06:33)