"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。
アゲハ採集会 番外編 [ファーブル会]
GWはいつものように何回か昆虫採集会を企画しました。
アゲハチョウの仲間が発生し始める時期なので、三浦半島方面でアゲハ採集会を開催。
国内にはアゲハと名の付くチョウが10種類います。
三浦半島はそのすべてが観察できる場所なのです。
今回もほぼすべてのアゲハが観察できました。

が、本記事ではアゲハの写真はこの一枚だけ。
番外編ということで、その他に観察できた虫たちを紹介します。
1回目は4月29日、自由採集の時間になり、採集エリアを離れ、獣道に近い散策路に侵入しました。
灌木が生い茂っている尾根道ですが、山の南側のため所々に明るい陽だまりがあります。
近くに小流があるのでしょう、去年と同じ場所でまたこの子がお出迎えしてくれました。

未成熟の男の子も観察できました。(←普通に読むと変な言い回しですね)

実は、一人で参加していた中学生の子と一緒に歩いていました。
オサムシやマイマイカブリに興味があるというので、じゃあ一緒に探しに行こうと誘ったのです。
獣道をしばらく進むと篠竹の茂るエリアになったので、「この辺りオサムシポイントだよ」と
教えてまもなく、後ろをついてきている彼の「あ、アオオサ!」という喜声。
さすがに目がいい。すぐ足元にいましたが写真を撮る余裕はありません。すぐ確保。
元の場所に戻ってきて、彼に獲物を渡しがてらあらためて撮影しました。

三浦半島のアオオサムシは鞘翅の緑色が明るくて、特に辺縁はネオンのように輝くのがいます。
が、この個体はやや褐色がかっていて渋い色でした。 でも縁取りの美しさはわかると思います。
もう一種、獣道を抜ける直前、彼が倒木の上に見つけた虫は。

約12ミリ。アリに見えますがハチです。 ミカドアリバチのメスには翅がないのです。
こちらもハチ。

いわゆる クマバチ ですが、オスは手に持っても大丈夫です。 針がないので刺しません。
ハムシやオトシブミの季節ですが、ゾウムシくんたちを紹介します。
この子は普通種ですが、なかなか撮影がむずかしい子。
ゾウムシたちは一般に過敏で、おどろくと落下したり死んだふりをしたり。
そうでなくてもすぐに触覚や脚を縮めてしまうので、いい写真が撮りづらいのです。

別名パンダゾウムシ、ちょっとぼーっとしていたようです。
この子も普通種ですがちょっと小ぶり。

クズやハギによくいますが、タンポポの花にとまっているのはちょっとめずらしいかもしれません。

5月4日、同じ場所で2回目を催行しました。
駅から採集場所へ向かう途中、まったく想定外の虫を見つけた子がいました。

いておかしくはないのですが、三浦半島に分布しているという事実がわかりました。
さて、今回は採集エリアに着いてすぐ、オサトラップを仕掛けに行ったのです。
もちろん設置場所は獣道のオサムシポイント。
前回とひょっとしたら同じ個体かもしれませんが、成熟オスが同じ場所でお出迎え。

なぜか胴体をしならせていました。
未成熟メスも観察できました。(1回目とは別個体かと)

トラップの結果はのちほど。

アゲハはジャコウアゲハは♂♀ともに多数観察。前回見られなかったモンキアゲハも観察できました。
番外編なので、他の虫たちを。
この子はちびっ子、5ミリくらいしかありません。

この虫はこれからたくさん観察できると思います。

この子も再登場。

さて、みんなでお昼を食べて、一旦解散となったあと、トラップを回収にいきました。
結果は・・・大漁でした。(ほんの3時間あまりで)

7個かけて、6匹採集。この場所は明らかに個体数が多いのだと思います。

参加者に配って解散となりました。
三浦半島の花たち。
広場の花壇に植えられていました。

こちらは野生。

ぽつぽつと複数株。

これは獣道の野生の群落。

これも野生。クレマチスの仲間だと思いますが。

今日の湯加減
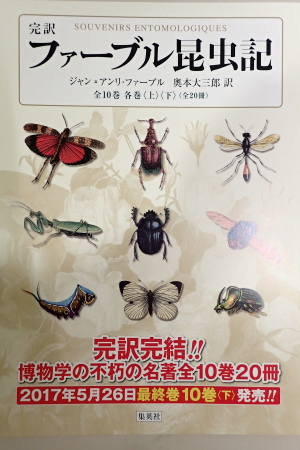
アゲハチョウの仲間が発生し始める時期なので、三浦半島方面でアゲハ採集会を開催。
国内にはアゲハと名の付くチョウが10種類います。
三浦半島はそのすべてが観察できる場所なのです。
今回もほぼすべてのアゲハが観察できました。

ジャコウアゲハ (アゲハチョウ科)
が、本記事ではアゲハの写真はこの一枚だけ。
番外編ということで、その他に観察できた虫たちを紹介します。
1回目は4月29日、自由採集の時間になり、採集エリアを離れ、獣道に近い散策路に侵入しました。
灌木が生い茂っている尾根道ですが、山の南側のため所々に明るい陽だまりがあります。
近くに小流があるのでしょう、去年と同じ場所でまたこの子がお出迎えしてくれました。

アサヒナカワトンボ ♀ (カワトンボ科)
未成熟の男の子も観察できました。(←普通に読むと変な言い回しですね)

同上 ♂ (カワトンボ科)
実は、一人で参加していた中学生の子と一緒に歩いていました。
オサムシやマイマイカブリに興味があるというので、じゃあ一緒に探しに行こうと誘ったのです。
獣道をしばらく進むと篠竹の茂るエリアになったので、「この辺りオサムシポイントだよ」と
教えてまもなく、後ろをついてきている彼の「あ、アオオサ!」という喜声。
さすがに目がいい。すぐ足元にいましたが写真を撮る余裕はありません。すぐ確保。
元の場所に戻ってきて、彼に獲物を渡しがてらあらためて撮影しました。

アオオサムシ (オサムシ科)
三浦半島のアオオサムシは鞘翅の緑色が明るくて、特に辺縁はネオンのように輝くのがいます。
が、この個体はやや褐色がかっていて渋い色でした。 でも縁取りの美しさはわかると思います。
もう一種、獣道を抜ける直前、彼が倒木の上に見つけた虫は。

ミカドアリバチ ♀ (アリバチ科)
約12ミリ。アリに見えますがハチです。 ミカドアリバチのメスには翅がないのです。
こちらもハチ。

キムネクマバチ ♂ (ミツバチ科)
いわゆる クマバチ ですが、オスは手に持っても大丈夫です。 針がないので刺しません。
ハムシやオトシブミの季節ですが、ゾウムシくんたちを紹介します。
この子は普通種ですが、なかなか撮影がむずかしい子。
ゾウムシたちは一般に過敏で、おどろくと落下したり死んだふりをしたり。
そうでなくてもすぐに触覚や脚を縮めてしまうので、いい写真が撮りづらいのです。

オジロアシナガソウムシ (ゾウムシ科)
別名パンダゾウムシ、ちょっとぼーっとしていたようです。
この子も普通種ですがちょっと小ぶり。

コフキゾウムシ (ゾウムシ科)
クズやハギによくいますが、タンポポの花にとまっているのはちょっとめずらしいかもしれません。
5月4日、同じ場所で2回目を催行しました。
駅から採集場所へ向かう途中、まったく想定外の虫を見つけた子がいました。

コカブトムシ ♀ (コガネムシ科)
いておかしくはないのですが、三浦半島に分布しているという事実がわかりました。
さて、今回は採集エリアに着いてすぐ、オサトラップを仕掛けに行ったのです。
もちろん設置場所は獣道のオサムシポイント。
前回とひょっとしたら同じ個体かもしれませんが、成熟オスが同じ場所でお出迎え。

アサヒナカワトンボ ♂ (カワトンボ科)
なぜか胴体をしならせていました。
未成熟メスも観察できました。(1回目とは別個体かと)

同上 ♀ (カワトンボ科)
トラップの結果はのちほど。
アゲハはジャコウアゲハは♂♀ともに多数観察。前回見られなかったモンキアゲハも観察できました。
番外編なので、他の虫たちを。
この子はちびっ子、5ミリくらいしかありません。

ヨツボシムナボソコメツキ (コメツキムシ科)
この虫はこれからたくさん観察できると思います。

ヒメビロウドコガネ (コガネムシ科)
この子も再登場。

コフキゾウムシ (ゾウムシ科)
さて、みんなでお昼を食べて、一旦解散となったあと、トラップを回収にいきました。
結果は・・・大漁でした。(ほんの3時間あまりで)

7個かけて、6匹採集。この場所は明らかに個体数が多いのだと思います。

アオオサムシ (オサムシ科)
参加者に配って解散となりました。
オマケ
三浦半島の花たち。
広場の花壇に植えられていました。

エビネ
こちらは野生。

キンラン
ぽつぽつと複数株。

同上
これは獣道の野生の群落。

コバノタツナミ
これも野生。クレマチスの仲間だと思いますが。

ハンショウヅル ?
今日の湯加減
恒例の新潟遠征に出かけますので予約投稿です。
ちょっと天気が心配ですが、日本海側は午後から回復するという予想。
昆虫採集に行くわけではないのですが・・
毎年会える虫。はじめて観察する虫。
とにかく色々な虫たちに会えることを期待しています。
またレポートします。
ところで、今月26日、ついに「完訳ファーブル昆虫記」の最終巻が発売になります。
奥本先生の12年にわたるお仕事。まさにライフワークの完結というところでしょうか。
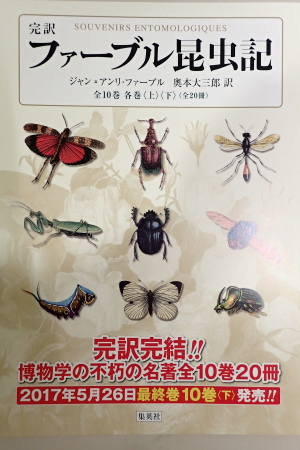
2017-05-13 12:00
nice!(25)
コメント(11)
"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。





こんにちは^^
虫の種類も多いですね~ 先日わたくしも虫を写しましたが小さすぎて(><;
ヨツボシムナボソコメツキは模様が良いですね。
by mimimomo (2017-05-13 15:22)
ゾウムシ、、やはりその姿、顔立ちにこんにちわと、挨拶したくなります、でも、過敏だから。死んだふりなんかして知らんふりかな、
ファーブル昆虫記、高校生の頃に読みかえしました
面白さを理解したのは、その時です
by engrid (2017-05-13 17:17)
本格的な64さんたちの季節ですねぇ♪
刺す64に好かれる私はすでに手作り虫除けが欠かせません^^;
だからあまり64に会わないのかも(笑)
by よしころん (2017-05-13 18:41)
やっと最近カワトンボが見られるようになってきました。
それと共になんの虫か、分からないうちに2カ所も刺されて
腫れあがってってしまいました。
by g_g (2017-05-13 20:31)
えぇ!クマバチって手で持てるんだ!
オスなら・・・飛んでいる時にオスメス見分けるのが私にはできないかも。(^_^ゞ
by 路渡カッパ (2017-05-13 23:08)
ハチの目 カワイイですね♪
by ねこじたん (2017-05-15 08:23)
>mimimomoさん
小さな被写体はほんとたいへんですよね^^;
ヨツボシムナボソコメツキは超ちびっこですが、いい色合いですね♪
>engridさん
目があったらコロンです^^;
昆虫記はオトナになってからも面白いと思います。
完訳版もぜひ♪
>よしころんさん
虫屋も蚊などが多い場合はスプレーします^^;
ところで、手作りですか??
>g_gさん
それはそれはお大事に・・虫じゃないかもですが・・^^;
>路渡カッパさん
ホバリングして哨戒しているのはまずオスですね。
あと、顔を見ればすぐわかります^^
>ねこじたんさん
クマバチはまんまるだしね^^
by ぜふ (2017-05-15 23:52)
こんにちは。
ゾウムシを初めて見たときはビックリしました。(@_@;)
見たのは一度だけでしたが・・・
by yakko (2017-05-18 13:34)
ゾウムシが可愛く撮れていますね。
たしかに風で枝が揺れてるのを手で止めるだけで死んだふりして転げ落ちます。
by 響 (2017-05-18 18:18)
おお、「縁取りの美しさ」、分かります^^;。
ゾウムシの体表の、モコモコというかザラザラというか、
苔むしたような感じが面白いです。
コカブトムシ...これ、カブトムシなんですねぇ。
by sakamono (2017-05-18 21:47)
>yakkoさん
びっくりしたということは、それなりに大きい子でしょうね^^
>響さん
マンガチックな瞳がいいですよね♪
目を合わせてもいけません^^
>sakamonoさん
もっと分かりやすい子もいるんですけどね・・
コカブトはカブトムシとはまったく似てないですね^^;
by ぜふ (2017-05-19 06:46)