"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。
虫モ [ファーブル会]
5月21日はファーブル会写真部の部活で裏高尾へ行きました。
新入部員候補2名を連れての昆虫撮影体験会。
部員は、というよりも昆虫撮影をする方はわかると思いますが、普通撮影はひとりで行きます。
(このブログの探虫行もそうです)

でもグループで行くのも、それはそれでとても楽しくていいものです。
トレッキング/ハイキングが目的ではないので、駅から地元のNさんの車で目的地まで向かいました。
その道中、両側に民家が立ち並ぶ1.5車線のバス通りをゆっり走る車の助手席から窓外を眺めていると、
Nさんが「あそこの柚子の木はいいポイントなんだよね」と左前方のガードレールの外の木を指さしました。
遠くからでも、アゲハらしいチョウなどが白い花に飛びまとわっているのが分かりました。
さらに徐行してその木を通り過ぎようとしたとき、脳内コンチューターが激しく反応しました。
コンチューターの信号を受信した目は特徴的な飛び方をする、特徴的な色と形の虫を見逃しませんでした。
「あ!アオバセセリじゃないですか?!」
「いる可能性はありますよ」
すぐ側の無人野菜販売所がある空き地に車をとめてもらいました。(その間にあわててカメラの準備)
久しぶりに持ち出したイチガンを首にかけてさっきの木に近寄ると、アオスジアゲハが何頭も群れているのが確認できましたが、ターゲットは違う。
よおく目を凝らせていると・・いました。

形はセセリチョウらしさ満点ですが、明らかにひとまわりビッグ。 こんな青い色したセセリもこの子だけ。
そしてもうひとつの特徴は飛ぶ速さ。 セセリ界のジェット戦闘機だと思います。
この写真を撮った0.5秒後には視界から消えていました。
それでも、アオバセセリに出迎えてもらえるなんて、何という幸先のよさなのでしょうと皆でよろこびました。
グループでの撮影会ということで、すでにワクワクしていたのに、期待感メーターの針はもう振り切れ寸前です。

目的地に着いて、それぞれもう一度装備を整えるのももどかしく、さっそく林道へ突入しました。
葉っぱの上でじっとしているジョウカイボンがいたので、その子で試し撮りをするメンバー。
この子もなぜか葉の上でじっとしていたので、試し撮り・・というよりも本番最初のモデルになってもらいました。

ミツバチと顔かたちが似ていますが、この子も一回り大きい。
この派手な金髪をしているのはオスで、働き蜂のメスは黒髪というのもミツバチと違うところです。
これも似た色をして、葉の上でじっとしていました。

あまりに目に付いたので思わず撮ってしまいましたが虫ではありません。 琥珀でしょうか?
前週、新潟でも観察したハムシ(ダマシ)もいました。

前記事でも書きましたが、この虫は以前ハムシダマシ科として分類されていました。
その通り、ぱっと見はハムシだと思う虫です。
しかし、ハムシダマシ科がゴミムシダマシ科に統合されてしまったために、ゴミムシダマシの仲間になりました。
ウスバアゲハのように、アオハムシダマシがアオゴミムシダマシと改名されることはないと思います。
実は、スジコガシラゴミムシダマシというゴミムシに似た虫がいて、ハムシダマシ科に分類されていました。
この子は晴れてゴミムシダマシの仲間に入れてもらえてほっとして・・いるわけはないでしょうけど。
まだ他にも・・

この子はハムシかゴミムシダマシかはたまた・・


林道の路上にはチョウもいます。

葉の上にもいたのでカメラを変えて。

一方はイチガン、一方はコンデジで撮りましたが、どちらか分かりますか?(どちらでもいいですね)
仮にも写真部の部活ですので、もうひとつ比較写真を。
オナガアゲハ(アゲハチョウ科)ですが、少しだけ露出を変えて撮影してみました。


どちらも少しだけコントラストを上げて少しだけトリミングしています。
この虫もこの時期、路上でよく屯しているそうです。

アサギマダラも飛来しましたが、この子たちのように着地して吸水するはずもなく、あえなく飛び去りました。
その代わりというわけではもちろんないのですが、こんな子が葉の上にとまって撮らせてくれました。

顔には出さないようにしましたが、この日2種目のサプライズでぐっとテンションがあがりました。
というわけで次から次へと格好の被写体たちが現れるので、全く前に進めません。(新入部員も進みません)
さらにこの子にもびっくり。

このビビッドさに気圧されてしばらく何か分かりませんでしたが、アワフキムシの幼虫だと判明。

トンボもいました。

サナエトンボの仲間(ダビドサナエ?)かと思いますが分かりません。
みんなでお昼を食べているとペアもやってきました。

こちらは渓流沿いの葉の上に。

目玉しか見えていませんが、このトンボはおそらく。

そしてこの日の主役の登場。

よくミヤマカワトンボを観察できる、渓流と散策路が交差する好ポイントに行ってみると、まさに撮ってください
とばかりに、流れの上にせり出した葉の上に。
そういう場所でテリトリーを張るのが彼らの習性ではありますが、ニンゲンの目の高さより下で、順光で、
正面あるいは横位置で撮影できる位置にとまってくれることはなかなかありません。
そういうアングルになるようにこちらが移動すると、気配を察知して逃げたり移動したりすることがままあります。
ところがこのペアはまるでプロのモデルのように、最初からステージの上でスタンバイしてくれていたようでした。
撮影隊が取り囲んでかなり接近してもピタリとポーズを決めたまま。
彼らがもしこのブログの読者なら、”読者モデル”というところでしょうけど、この子たちはさしずめ”虫モ”?
ずいぶん長い間、撮影タイムは続きましたが、いやな顔一つせずに大人しくしてくれていました。
こんなことははじめてでしたが、新入部員候補の方たちの虫運のよさのおかげだったのかも。
予定の時刻は過ぎていましたが、予定の行程の半分くらいしか進みませんでした。
残業することにして、もう少しだけ上流へ行きました。
そこではめぼしい昆虫には会えませんでしたが、この子は何匹か。

帰り道はさすがに行きと同じ時間はかかりませんでしたが、虫運のいい新入部員候補のひとりは、
「オオトラフコガネとアカスジキンカメムシにも会いたい」
とぜいたくなことを言い放ってましたが、ザンネンながら見送りには来てくれませんでした。
もしほんとに会えていたら虫運のよさなど通り越してオカルトになってしまうので、これでよかったと思います。
今日の湯加減
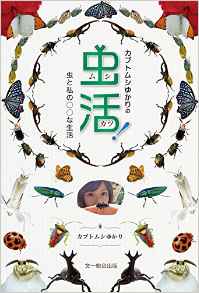
新入部員候補2名を連れての昆虫撮影体験会。
部員は、というよりも昆虫撮影をする方はわかると思いますが、普通撮影はひとりで行きます。
(このブログの探虫行もそうです)

でもグループで行くのも、それはそれでとても楽しくていいものです。
トレッキング/ハイキングが目的ではないので、駅から地元のNさんの車で目的地まで向かいました。
その道中、両側に民家が立ち並ぶ1.5車線のバス通りをゆっり走る車の助手席から窓外を眺めていると、
Nさんが「あそこの柚子の木はいいポイントなんだよね」と左前方のガードレールの外の木を指さしました。
遠くからでも、アゲハらしいチョウなどが白い花に飛びまとわっているのが分かりました。
さらに徐行してその木を通り過ぎようとしたとき、脳内コンチューターが激しく反応しました。
コンチューターの信号を受信した目は特徴的な飛び方をする、特徴的な色と形の虫を見逃しませんでした。
「あ!アオバセセリじゃないですか?!」
「いる可能性はありますよ」
すぐ側の無人野菜販売所がある空き地に車をとめてもらいました。(その間にあわててカメラの準備)
久しぶりに持ち出したイチガンを首にかけてさっきの木に近寄ると、アオスジアゲハが何頭も群れているのが確認できましたが、ターゲットは違う。
よおく目を凝らせていると・・いました。

アオバセセリ (セセリチョウ科)
形はセセリチョウらしさ満点ですが、明らかにひとまわりビッグ。 こんな青い色したセセリもこの子だけ。
そしてもうひとつの特徴は飛ぶ速さ。 セセリ界のジェット戦闘機だと思います。
この写真を撮った0.5秒後には視界から消えていました。
それでも、アオバセセリに出迎えてもらえるなんて、何という幸先のよさなのでしょうと皆でよろこびました。
グループでの撮影会ということで、すでにワクワクしていたのに、期待感メーターの針はもう振り切れ寸前です。
目的地に着いて、それぞれもう一度装備を整えるのももどかしく、さっそく林道へ突入しました。
葉っぱの上でじっとしているジョウカイボンがいたので、その子で試し撮りをするメンバー。
この子もなぜか葉の上でじっとしていたので、試し撮り・・というよりも本番最初のモデルになってもらいました。

コマルハナバチ ♂ (ミツバチ科)
ミツバチと顔かたちが似ていますが、この子も一回り大きい。
この派手な金髪をしているのはオスで、働き蜂のメスは黒髪というのもミツバチと違うところです。
これも似た色をして、葉の上でじっとしていました。

あまりに目に付いたので思わず撮ってしまいましたが虫ではありません。 琥珀でしょうか?
前週、新潟でも観察したハムシ(ダマシ)もいました。

アオハムシダマシ (ゴミムシダマシ科)
前記事でも書きましたが、この虫は以前ハムシダマシ科として分類されていました。
その通り、ぱっと見はハムシだと思う虫です。
しかし、ハムシダマシ科がゴミムシダマシ科に統合されてしまったために、ゴミムシダマシの仲間になりました。
ウスバアゲハのように、アオハムシダマシがアオゴミムシダマシと改名されることはないと思います。
実は、スジコガシラゴミムシダマシというゴミムシに似た虫がいて、ハムシダマシ科に分類されていました。
この子は晴れてゴミムシダマシの仲間に入れてもらえてほっとして・・いるわけはないでしょうけど。
まだ他にも・・

ヒゲナガルリマルノミハムシ (ハムシ科)
この子はハムシかゴミムシダマシかはたまた・・

未同定
林道の路上にはチョウもいます。

ミスジチョウ (タテハチョウ科)
葉の上にもいたのでカメラを変えて。

一方はイチガン、一方はコンデジで撮りましたが、どちらか分かりますか?(どちらでもいいですね)
仮にも写真部の部活ですので、もうひとつ比較写真を。
オナガアゲハ(アゲハチョウ科)ですが、少しだけ露出を変えて撮影してみました。

F5.0 SS1/80 ISO100 -0.3EV

F3.5 SS1/320 ISO100 -0.7EV
どちらも少しだけコントラストを上げて少しだけトリミングしています。
この虫もこの時期、路上でよく屯しているそうです。

マドガ (マドガ科)
アサギマダラも飛来しましたが、この子たちのように着地して吸水するはずもなく、あえなく飛び去りました。
その代わりというわけではもちろんないのですが、こんな子が葉の上にとまって撮らせてくれました。

スミナガシ (タテハチョウ科)
顔には出さないようにしましたが、この日2種目のサプライズでぐっとテンションがあがりました。
というわけで次から次へと格好の被写体たちが現れるので、全く前に進めません。(新入部員も進みません)
さらにこの子にもびっくり。

このビビッドさに気圧されてしばらく何か分かりませんでしたが、アワフキムシの幼虫だと判明。
トンボもいました。

サナエトンボの仲間(ダビドサナエ?)かと思いますが分かりません。
みんなでお昼を食べているとペアもやってきました。

こちらは渓流沿いの葉の上に。

目玉しか見えていませんが、このトンボはおそらく。

ニホンカワトンボ (カワトンボ科)
そしてこの日の主役の登場。

ミヤマカワトンボ ペア (カワトンボ科)
よくミヤマカワトンボを観察できる、渓流と散策路が交差する好ポイントに行ってみると、まさに撮ってください
とばかりに、流れの上にせり出した葉の上に。
そういう場所でテリトリーを張るのが彼らの習性ではありますが、ニンゲンの目の高さより下で、順光で、
正面あるいは横位置で撮影できる位置にとまってくれることはなかなかありません。
そういうアングルになるようにこちらが移動すると、気配を察知して逃げたり移動したりすることがままあります。
ところがこのペアはまるでプロのモデルのように、最初からステージの上でスタンバイしてくれていたようでした。
撮影隊が取り囲んでかなり接近してもピタリとポーズを決めたまま。
彼らがもしこのブログの読者なら、”読者モデル”というところでしょうけど、この子たちはさしずめ”虫モ”?
ずいぶん長い間、撮影タイムは続きましたが、いやな顔一つせずに大人しくしてくれていました。
こんなことははじめてでしたが、新入部員候補の方たちの虫運のよさのおかげだったのかも。
オマケ
予定の時刻は過ぎていましたが、予定の行程の半分くらいしか進みませんでした。
残業することにして、もう少しだけ上流へ行きました。
そこではめぼしい昆虫には会えませんでしたが、この子は何匹か。

ウスアカオトシブミ (オトシブミ科)
帰り道はさすがに行きと同じ時間はかかりませんでしたが、虫運のいい新入部員候補のひとりは、
「オオトラフコガネとアカスジキンカメムシにも会いたい」
とぜいたくなことを言い放ってましたが、ザンネンながら見送りには来てくれませんでした。
もしほんとに会えていたら虫運のよさなど通り越してオカルトになってしまうので、これでよかったと思います。
今日の湯加減
今日は写真部の屋内部活の日です。
それぞれの作品を持ち寄るのですが、みな遠慮してか作品を自慢しあうワケでもなく、批評しあうワケでもなく。
でも、この部活に参加したメンバーは(新入部員も)この日の写真を印刷して見せあうことにしています。
どれを持って行くか、選び方も考えどころですが、虫モのミヤマカワトンボはやはりはずせないか。
他のメンバーが何を持ってくるか想像しながら、他にもひとつふたつ選びました。
写真部メンバーの作品はファーブル館内に展示していますが、
候補生のひとりもめでたく正式入部し、彼女の写真もさっそく掲載しました。
こちらの虫活本も好評のようです。
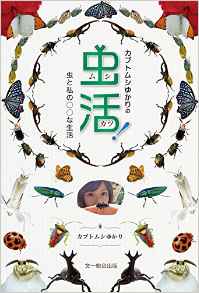
"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。





こんばんは^^
まぁ~次から次へと・・・やはり虫好きさんのところにはちゃんと心得てモデルを務めてくれるのでしょうかしらね? 今日わたくしは
入笠湿原へ行ってきました。色んな種類の蝶がいるのですが、一度たりとも止まってくれませんでした(-。- 収穫0・・・
by mimimomo (2016-06-18 21:08)
羨ましいぐらい昆虫が寄ってきますね
でも留まってくれないと私は撮れないのが悩み・・・
by g_g (2016-06-19 08:08)
こころは、マックスにワクワクに、、
緑の季節に、虫達も映えますね
ビビッドな色合いに、ビックリ、
でも、琥珀?しばし記事を読む前に、なになにと目を凝らして
凝視していました、カワトンボの優雅な姿、美しいな
by engrid (2016-06-19 08:57)
スミナガシ、綺麗な羽ですよね!
by sasasa (2016-06-19 21:20)
コマルハナバチ、うみちゃんみたいで可愛い!(笑)
by リュカ (2016-06-19 21:57)
>mimimomoさん
入笠山は虫屋にも人気スポットです♪
チョウチョ撮れませんでしたか・・・><
>g_gさん
基本的にとまっている虫が被写体ですね。
虫モさんは微動だにしませんでした^^
>engridさん
そう、虫たちももっとも活発な季節ですね♪
虫モさんはとてもいい子でした^^
>sasasaさん
スミナガシはそちらにはいないと思いますが・・?
>リュカさん
ヘソてんはしなかったですけどね^^
by ぜふ (2016-06-19 22:24)
脳内コンチューターも素早い撮影も
コンデジも素晴らしいですね!
ワクワク感伝わってきました
今年はトンボじっくり撮りたいなぁ^^
by shino* (2016-06-21 08:15)
このところ裏高尾に行ってませんので、懐かしです。たくさんの虫に出会えてたのしい所ですね。私には虫モくんたちが少なくてたいへんです。
by アサギいろ (2016-06-22 00:00)
>shino*さん
最近のコンデジは優秀でイチガンの出番が・・^^;
ぜひトンボをじっくり撮って見せてください♪
>アサギいろさん
こんな虫モさんはめずらしいですね^^
アサギマダラは皆つれなく通り過ぎていきましたよ^^;
by ぜふ (2016-06-22 06:43)
琥珀みたいなモノ、何でしょうね。すごくキレイですね。
ミヤマカワトンボ、手前のヤツが、ちょっと小首を傾げて
こちらを見て、ポーズを取っているようです^^;。
by sakamono (2016-06-22 22:26)
アワフキムシの幼体は新種かと思いました。
琥珀はもし琥珀なら磨いたら宝石に?
by 響 (2016-06-24 17:29)
>sakamonoさん
いまさらながら持って帰ればよかったと^^;
ミヤマカワトンボのペアはずっとポーズをとってくれていました♪
>響さん
どうして出てきていたのかはわかりませんでしたが、引越し?^^
琥珀モドキはこのままで十分な輝きでしたが・・拾って来ればよかったぁ^^;
by ぜふ (2016-06-25 09:30)