"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。
越冬モード [観察会]
12月20日、HFの観察会に行ってきました。
前回訪れたのが11月1日。
その頃は晩秋だと思っていたのですが、それからもチバの秋は長く続きました。
冬への準備ができていなかったところへ、12月に入って数日間、がくっと気温が下がったので寒さが厳しく感じられましたが、その後は暖かい日が続いたり、また少し寒い日が来たり。
今のところ、”暖冬”という予報が当たっていると思われるチバです。
特にここのところ、まるで春の三寒四温のようですが、この日も風がなく穏やかな観察日和でした。
とはいえ、冬は冬なので、越冬中の昆虫観察のシーズン到来です。

この虫の説明はのちほど。
集合場所周辺でカマキリのタマゴをいくつか観察し、林の中ではクサカゲロウも観察しました。(写真なし)
ジャノヒゲの実を採ったり、カタツムリの子供を観察したり、ちょっと変わった赤い実の説明をききました。

鳥が好きな実のようで、食べられたあとはカノコ模様になるのだそうです。
しばらくして観察指導員の方が「ちょっと面白いものがあります」と声をかけてくれました。
誘導されたのは太いケヤキの木の根元。
落ち葉をかえしてみてくださいというので、少しずつ手ではらっていくと・・

HFではレギュラーメンバーのカメムシですが、越冬しているところを観察したのははじめてでした。
(集団越冬もするのではないかと思いますがこの子はひとりぽっちでした)
ケヤキの木の皮の下にも別のカメムシがいました。

このカメムシは複数観察できました。(かつ初見でした)

林を抜けると谷津田に出るので見通しが開け明るくなり、体感温度が一気に上がります。
林と休耕田の間の散策路では、地面にはコバネイナゴ、樹上にはムラサキシジミが観察できました。(写真なし)
陽だまりにはアブたちが屯していました。

そして、とある一本の木にだけアブラムシの集団が。

ついている木がゴンズイと教えていただき、さらにゴンズイにつくアブラムシということで同定しましたが・・はて。
やはり今年は暖冬なのか、こんな虫も観察できました。

複数いましたが、これから越冬するのでしょうね。
この子は越冬できませんが、12月下旬に観察したのははじめてだと思います。

この時期にしては翅も傷んでなくて、シャッターを押した直後、元気に飛び去って行きました。

舗装している農道まででて、子供たちとジャノヒゲ遊びをしました。
ジャノヒゲの外皮(青い皮)をはぐと、中から真珠のような白い実がでてきます。

これを地面に落とすと、まるでスーパーポールのように弾むのです。
子供の頃やりませんでしたかと尋ねられましたが、残念ながらこの遊びの記憶はありませんでした。
そして復路はまた別のコースを辿って戻ったのですが、その途中で観察したのが扉の写真の虫でした。
(これも観察指導員の方が予め見つけてくれていた)
ヤツデの葉の裏でじっとしている1センチにも満たない昆虫。

ちょうどクリスマスにちなんだような、背中の”X”マークが特徴。
セモンカメノコハムシともいうようですが、この時期だけはクリスマスハムシでもいいかな?
サクラ類が食樹なのですが、指導員の方によると10月からこの葉の裏でじっとしているとのことです。
2か月もじっとしているなんて死んでいるんじゃないかって疑問の声が聞こえて来そうですが、このハムシの仲間は死んでしまうと透明の部分が変色して透明ではなくなるのです。
つまり、この子も越冬態勢なのです。
うちの子たちも徐々に越冬モードに入っているのですが、この子たちはケースの中で飛び回るほど活発。

採集した場所は同じですが、色がそれぞれ微妙に違います。
ファーブル館で生態展示して好評だったハンミョウたちも越冬モードに入ってもらうことにしました。
(年末年始は休館するため)
水槽の底においてある、隠れ家の木の皮をどかすと・・

7頭のハンミョウが身を寄せ合っていました。(撮影するのに時間がかかったため少しばらけてしまった)
飼育ケースに引っ越してもらい、スタッフの自宅に持ち帰ってもらいました。

今日の湯加減
前回訪れたのが11月1日。
その頃は晩秋だと思っていたのですが、それからもチバの秋は長く続きました。
冬への準備ができていなかったところへ、12月に入って数日間、がくっと気温が下がったので寒さが厳しく感じられましたが、その後は暖かい日が続いたり、また少し寒い日が来たり。
今のところ、”暖冬”という予報が当たっていると思われるチバです。
特にここのところ、まるで春の三寒四温のようですが、この日も風がなく穏やかな観察日和でした。
とはいえ、冬は冬なので、越冬中の昆虫観察のシーズン到来です。

セモンジンガサハムシ (ハムシ科)
この虫の説明はのちほど。
集合場所周辺でカマキリのタマゴをいくつか観察し、林の中ではクサカゲロウも観察しました。(写真なし)
ジャノヒゲの実を採ったり、カタツムリの子供を観察したり、ちょっと変わった赤い実の説明をききました。

サネカズラ (と聞いたような・・)
鳥が好きな実のようで、食べられたあとはカノコ模様になるのだそうです。
しばらくして観察指導員の方が「ちょっと面白いものがあります」と声をかけてくれました。
誘導されたのは太いケヤキの木の根元。
落ち葉をかえしてみてくださいというので、少しずつ手ではらっていくと・・

エサキモンキツノカメムシ (ツノカメムシ科)
HFではレギュラーメンバーのカメムシですが、越冬しているところを観察したのははじめてでした。
(集団越冬もするのではないかと思いますがこの子はひとりぽっちでした)
ケヤキの木の皮の下にも別のカメムシがいました。

ミヤマカメムシ (カメムシ科)
このカメムシは複数観察できました。(かつ初見でした)
林を抜けると谷津田に出るので見通しが開け明るくなり、体感温度が一気に上がります。
林と休耕田の間の散策路では、地面にはコバネイナゴ、樹上にはムラサキシジミが観察できました。(写真なし)
陽だまりにはアブたちが屯していました。

ヒラタアブの仲間
そして、とある一本の木にだけアブラムシの集団が。

ゴンズイノフクレアブラムシ ? (アブラムシ科)
ついている木がゴンズイと教えていただき、さらにゴンズイにつくアブラムシということで同定しましたが・・はて。
やはり今年は暖冬なのか、こんな虫も観察できました。

ハマベアワフキ ? (アワフキムシ科)
複数いましたが、これから越冬するのでしょうね。
この子は越冬できませんが、12月下旬に観察したのははじめてだと思います。

オオアオイトトンボ ♀ (アオイトトンボ科)
この時期にしては翅も傷んでなくて、シャッターを押した直後、元気に飛び去って行きました。
舗装している農道まででて、子供たちとジャノヒゲ遊びをしました。
ジャノヒゲの外皮(青い皮)をはぐと、中から真珠のような白い実がでてきます。

これを地面に落とすと、まるでスーパーポールのように弾むのです。
子供の頃やりませんでしたかと尋ねられましたが、残念ながらこの遊びの記憶はありませんでした。
そして復路はまた別のコースを辿って戻ったのですが、その途中で観察したのが扉の写真の虫でした。
(これも観察指導員の方が予め見つけてくれていた)
ヤツデの葉の裏でじっとしている1センチにも満たない昆虫。

ちょうどクリスマスにちなんだような、背中の”X”マークが特徴。
セモンカメノコハムシともいうようですが、この時期だけはクリスマスハムシでもいいかな?
サクラ類が食樹なのですが、指導員の方によると10月からこの葉の裏でじっとしているとのことです。
2か月もじっとしているなんて死んでいるんじゃないかって疑問の声が聞こえて来そうですが、このハムシの仲間は死んでしまうと透明の部分が変色して透明ではなくなるのです。
つまり、この子も越冬態勢なのです。
オマケ
うちの子たちも徐々に越冬モードに入っているのですが、この子たちはケースの中で飛び回るほど活発。

センチコガネ (コガネムシ科)
採集した場所は同じですが、色がそれぞれ微妙に違います。
オマケ その2
ファーブル館で生態展示して好評だったハンミョウたちも越冬モードに入ってもらうことにしました。
(年末年始は休館するため)
水槽の底においてある、隠れ家の木の皮をどかすと・・

ハンミョウ (オサムシ科)
7頭のハンミョウが身を寄せ合っていました。(撮影するのに時間がかかったため少しばらけてしまった)
飼育ケースに引っ越してもらい、スタッフの自宅に持ち帰ってもらいました。

今日の湯加減
昨日はファーブル館スタッフの忘年会でした。
会場が家からは遠かったため帰宅したのは真夜中過ぎ。
ちょっと疲れがたまっていたのか、今朝は久しぶりに超朝寝坊。
午前中は少しこの記事のために写真の整理をしただけ。
午後は前々記事のフユシャク観察のリベンジに行ってきました。
成果ありでした。その記事に追記しましたので、ご興味のある方はご覧ください。
↓ファーブル館でもぼちぼち売れています
"Wessay"とはWeb Essayを約めたオリジナルの造語です。
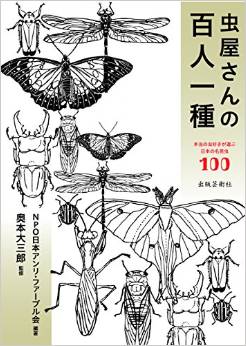





セモンカメノコハムシはピアスにしてみたい(笑)
でも死んでしまうと透明感がなくなってしまうんですね(^^;)
by barbie (2015-12-23 22:53)
ジャノヒゲ、そんな遊び方有ったんですね!!!
by g_g (2015-12-24 08:24)
暖冬は虫の世界にも
でも、サイクルに影響は出てこないのかな
サネカズラの赤が綺麗ですね、、食べられた後は見たことがないかなセモンカメノコハムシ、ゼリーで覆われてような、素敵な越冬の姿です
by engrid (2015-12-24 08:44)
セモンジンガサハムシ、あのゼリー温かいのかしら~^^
分けて欲しい(笑)
by よしころん (2015-12-24 09:22)
この寒い時でも虫の観察は出来るものなんですね~越冬中を見つけるって慣れてないと難しそう。
ことしは暖冬異変でしょうか、うちの庭でもアブの飛んでいるところを見ましたよ。
サネカズラ(別名ビナンカズラ)綺麗な実ですよね^^
by mimimomo (2015-12-24 09:35)
お早うございます。
ハムシはゼリーに包まれて越冬するんですね〜
ハンミョウは集団で越冬するんですか。
by yakko (2015-12-24 09:38)
この季節、虫を見かけないから存在をついつい忘れてしまいますが
ちゃんと越冬してるのですねー。
あらためて気づきました(笑)
by リュカ (2015-12-24 15:25)
>barbieさん
なるほど~
Xマークのデザインもおしゃれですからね^^
>g_gさん
はじめて知りましたが、やってみたらびっくりでした。
ぜひお試しを^^
>engridさん
暖冬でも、虫たちはもっと大きなサイクルをしっかり感じているんでしょうね。
サネカズラが鳥に食べられたあとはカノコ模様のボールみたいでした^^
>よしころんさん
ざんねんながら、これはゼリーではないんです。
身体自体が透き通っているんです。 あ、透き通った身体もいいですね^^
>mimimomoさん
これからは越冬昆虫のシーズンです^^
サネカズラの別名、調べましたら、なんと面白い由来ですね♪
>yakkoさん
ゼリーに包まれて越冬もいいですね^^
でもゼリーではないんです。自分の体なんです。
ハンミョウは美しい集団になります♪
>リュカさん
なんらかの形態でみな冬越しをしているわけですね。
常夏の国の昆虫はこの限りではないですけど^^
by ぜふ (2015-12-24 21:02)
カメコノって言った方が可愛いですよね。
透明なバリアをはったような姿がほんと面白いです。
はじめて見た時はビックリしました。
スーパーボールみたいになる遊びはやった事がないです。
by 響 (2015-12-27 01:11)
>響さん
透明な陣笠ももしあれば面白いですけどね^^
自然のスーパーボール、やってみてください。
by ぜふ (2015-12-27 10:46)
セモンカメノコハムシ、
こうして見ると綺麗ですね(^_^)
これで越冬しているのですね。
by sasasa (2015-12-27 16:04)
ジャノヒゲ遊びは知りませんでした。今度、どこかで見つけたら、絶対
やってしまうと思います^^;。
セモンカメノコハムシ、ブローチみたいですねー。
by sakamono (2015-12-29 23:47)
>さささん
もっと寒い日だと氷の中に閉ざされているように見えるかもしれませんね^^
>sakamonoさん
やってみてください。スーパーボールほどではないですが、弾みます♪
生きたままブローチになってくれるといいですね^^
by ぜふ (2015-12-30 17:59)
赤い実は 鳥さんに運んでもらいたいから
赤いと きいたな〜
弾む実 きになるな〜
by ねこじたん (2015-12-30 18:41)